人はどうことばを処理しているかという情報処理的な視点と、ノーム・チョムスキー(Noam Chomsky)の生成文法というインパクトなどから、1950〜60年代以来、新たな知的潮流を形作ってきた言語学。そのメッカであるMITなどで蓄積した基礎研究の知見を活かし、10年ほど前から言語教育、特に英語教育について意識的に発言し始めたという大津由紀雄教授。4月からは明海大学教授として「言語学ではほとんどの問題にけりがついていない」と、ことばの探求のおもしろさを伝授する。東京・三田にある慶應義塾大学 言語文化研究所に、大津由紀雄教授を訪ねた。
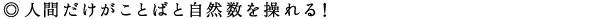
 人間の子どもは生まれてから徐々に母語を獲得していきますね。私は、心的なメカニズムと、子どもが外部から取り込む言語経験とが相互作用し、母語が出来上がる過程を明らかにしたいと考えています。ことばはヒトしか身につけることができない。同時に、ヒトなら誰でも母語を身につけます。人間のこころがどうことばを処理しているかを明らかにすることで、人間のこころの見えなかった部分が見えてくるだろうというのが、そもそもの発想です。
人間の子どもは生まれてから徐々に母語を獲得していきますね。私は、心的なメカニズムと、子どもが外部から取り込む言語経験とが相互作用し、母語が出来上がる過程を明らかにしたいと考えています。ことばはヒトしか身につけることができない。同時に、ヒトなら誰でも母語を身につけます。人間のこころがどうことばを処理しているかを明らかにすることで、人間のこころの見えなかった部分が見えてくるだろうというのが、そもそもの発想です。
そこで私は、2〜4歳ぐらいの子どもたちが母語の体系をどこまで獲得し、どのようにそれを構築したかを、実験と発話分析によって具体的に確かめていきます。母語の獲得には、ことばが使われる場面での様々な状況が密接に関係してきますが、それ以前にまずはことばの基本的な構造を子どもが手に入れていると考えられます。このことばの構造について、私が最も本質的だと考えるのは「入れ子」という性質ですね。たとえば「花子が歌っていた」という文は「花子が歌っていたと一郎が言った」と、より大きな文の一部になることができます。そして、その文は「花子が歌っていたと一郎が言ったと二郎が言った」とさらに大きな文の一部になることができます。入れ子ですね。そして、原理的には文を無限に入れ子状に大きくしていくことができます。英語でも話は同じで、たとえば、”John said that Jim said that Mary was singing.”という具合に、どんどん大きな文にしていくことができる。日本語、英語、そして、どの言語もこういう性質を持っているのです。普遍性といわれる性質です。でも、文を大きくしていったときに、日本語では、「…と一郎が言ったと二郎が言った」と、新たに付け加えられる部分が文の右側に寄っています。でも、英語では、”John said that Jim said that ….”と日本語とは逆に新たに付け加えられた部分が文の左側に寄っています。これは日本語と英語が持つ個性、個別性と呼ばれる性質です。ことばの普遍性と個別性はおそらく人間の脳が持つ性質を反映したものであると考えられます。
さっきの入れ子の話ですが、じつは、ことばだけでなく、自然数の体系も同様の性質を持っています。自然数1、2、3……は、1は自然数、そして、nが自然数ならば、n+1は自然数と規定しておくと、最大の自然数というものは存在しない。無限に大きくしていくことができるというシステムです。ことばにしても、自然数にしても、入れ子という仕組み持っていて、それを操ることができるのは人間だけ、ヒトだけです。どうして人間の脳だけがことばと数を操れるのか? ことばと数のどちらが先にできたのか?……
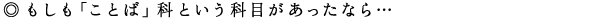
 ところで、ことばの性質を探っていく上で、これといった決まった方法は何もない、とチョムスキーは言っています。大切なのは「合理的に考える」ことであり、それだけが唯一の制約だ、と。
ところで、ことばの性質を探っていく上で、これといった決まった方法は何もない、とチョムスキーは言っています。大切なのは「合理的に考える」ことであり、それだけが唯一の制約だ、と。
普遍文法というのはチョムスキーの考え方ですが、ことばに人類共通の基盤があること、つまり、普遍性があるということを否定する言語学者は一人もいません。では、なぜ普遍性が存在するのだろうか?──人間の子どもは誰でも母語を身につけることができるのだけれども、生まれた時にはどの言語が母語になるか決まっているわけではない。生まれてから日本語に触れていれば日本語が母語に、英語に触れていれば英語が母語になる。つまり、後天的に決まる。そして、生まれてから触れる言語が何語であっても脳は対応できる。このことを説明する合理的な理由として、ことばは個別性ともに普遍性を持っており、その普遍性はことばに関して脳が対応できる範囲を反映したものと考えてはどうだろうか。こんな具合に考えるのです。もちろん、そう考えると決めたら、本当に普遍性が存在するのか、どんな普遍性が存在するのか、こうした点を探っていかなくてはなりませんし、その結果、徐々に浮かび上がってくる普遍性の姿がさきほどの母語獲得の話とどの程度うまく符合するのか、そういうことを考える必要があります。現在、研究の最前線ではそうした検討が世界規模でなされています。
また、この普遍性という視点から外国語学習を考えると、母語の仕組みを意識的に捉えることから出発して、普遍性を経由して、外国語の学習へ向かうという方法が効果的と考えられます。母語の場合には、たとえば、動詞の活用などの文法を勉強しなくても、不自由なく使えるではないかという意見もありますが、そのもとにある知識を意識化することで、外国語の学習に役立てることができます。さらに、母語の仕組みを意識化させることで、母語を効果的に使うことができるようにもなります。
たとえば、中学1年生の英語に出て来る「三単現の-s」でつまづく子が多いのは、「三単現」を理解するためには、「文の主語」、「数(単数とか、複数とか)」「人称」「現在」という動詞の時制などの概念がわからないといけません。そういった準備ができていない子どもたちがたくさんいるのです。英語では「三単現の-s」というものがあるのだから、それはそういうものだと覚えるしかないという取り組み方では英語が使えるようにはなりません。まずは、このような概念が日本語ではどのように使われているのか、いったん「ことば」の問題として考えてみたらどうだろうというのが私の提案です。
「数」ということを例にとりましょうか。日本語では、きりんが1頭でも、2頭でも「きりん」で形が変わらないことが多い。でも、「きりんたち」という言い方もできるでしょ。複数形ですよね。でも、そこからがおもしろい。「きりんたち」と言ったからといって、必ずしもきりんが複数頭いるとは限らない。このことに気づかせると、小学生なんか大喜びしますよ。「今朝きりんさんたちが動物園から逃げ出しました。さて、逃げたきりんさんは何頭でしょう?」──みんな、2頭とか、3頭とか答えます。そのとき、「ブー。逃げたキリンさんは1頭でした」と言うと子どもたちはみんな「うそだー」って言います。タネ明かしは──「みんな桃太郎さんのお話知ってるよね。桃太郎さん『たち』は鬼退治に鬼ヶ島へ行きました」。「桃太郎さん、何人?」(笑)
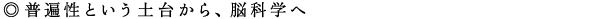
 言語学や認知科学における最近の話題のひとつに、言語の起源と進化というテーマがあります。これはつまり、近年、言語理論の研究が進んで明らかになってきた普遍性についての理解を土台として、普遍性を具体的に脳の問題、進化の問題として考えていこうというものなんですね。これからの言語学の方向性として、脳科学の知見を活かし、脳科学者との協力体制を築いていくことには、私も大いに期待を持っています。チョムスキーだけでなく、スティーブン・ピンカー(Steven Pinker)、レイ・ジャッケンドフ(Ray Jackendoff)といった著名な言語学者が脳科学者、人類学者、進化学者たちと意見を交わしながら、研究を進めています。じつは、去年(2012年)の3月に京都で言語の起源と進化に関する大きな国際会議が開催されました。
言語学や認知科学における最近の話題のひとつに、言語の起源と進化というテーマがあります。これはつまり、近年、言語理論の研究が進んで明らかになってきた普遍性についての理解を土台として、普遍性を具体的に脳の問題、進化の問題として考えていこうというものなんですね。これからの言語学の方向性として、脳科学の知見を活かし、脳科学者との協力体制を築いていくことには、私も大いに期待を持っています。チョムスキーだけでなく、スティーブン・ピンカー(Steven Pinker)、レイ・ジャッケンドフ(Ray Jackendoff)といった著名な言語学者が脳科学者、人類学者、進化学者たちと意見を交わしながら、研究を進めています。じつは、去年(2012年)の3月に京都で言語の起源と進化に関する大きな国際会議が開催されました。
脳の働きを画像化する「機能画像法」は、今のところ時間の解像能も空間の解像能も、言語の問題を本格的に取り扱うにはまだまだ足りない部分が多いのですが、技術の進歩は著しいので、これからの発展が大いに期待されるところです。言語学では古くから研究されている「時制」というテーマも、普遍性との関連で考えるとおもしろい。他の動物でも2つの事象を比べて「より前に起こった」「より後に起こった」という区別ならば出来るように思いますが、人間は、発話の時、視点が置かれている時、問題の事象が起こった時の関係を計算して時制を使っています。さらに、それに、進行(形)とか完了(形)とか、「アスペクト(相)」と呼ぶのですが、そういうシステムが絡み合ってきます。時制とアスペクトのシステムを子どもがどう発達させていくのか、脳はそのシステムをどう取り扱っているのか、興味はつきません。
また、時間表現は空間表現とも関係があります。われわれは時間軸の前方、つまり未来を向いて生きているように思っていますが、過去のことを指すのには、たとえば、「3年前」、未来の場合は「3年後」と表現している……と指摘されると不思議な感じがしますね。でも、「過去を振り返る」とも言いますよね。人は、読み取った時間的な関係と空間的な関係をコーディネイトして言語表現している──今後このようなことばと時間概念の関係も、探っていきたいと考えています。神経科学の関係者とのコラボも念頭に置いています。






