東大に、立ち見学生が出るほどの熱気に満ちた授業があるという。しかも文科系の学部生向け数学だ。こんなにも学生を惹きつけるものは何なのだろう? その授業とはどんなものか。講義を行う小林俊行教授に、数学を通して伝えたいものとは何かを聞いた。
◎準備に授業の10倍の時間をかける
 小林俊行さん。根源的な発見や新理論の創始などで、後世に残る重要な業績を挙げ、さらに今後も学問の最先端で活躍し続けることが期待される国際的に著名な研究者に授与される「フンボルト賞」を受賞した数学者である。2015年に国際学術誌に出版した論文12本は延べ300ページを超え、国際会議の招待講演は9回を数える。毎年このペースで成果を挙げながら、学部生の授業にも力を入れる。現在は、大学の制度上の調整により履修者数が制限されているものの、数年前までは立ち見や床座りの学生で、300人収容の大教室が溢れるような熱気につつまれる光景も頻繁に見られたという。
小林俊行さん。根源的な発見や新理論の創始などで、後世に残る重要な業績を挙げ、さらに今後も学問の最先端で活躍し続けることが期待される国際的に著名な研究者に授与される「フンボルト賞」を受賞した数学者である。2015年に国際学術誌に出版した論文12本は延べ300ページを超え、国際会議の招待講演は9回を数える。毎年このペースで成果を挙げながら、学部生の授業にも力を入れる。現在は、大学の制度上の調整により履修者数が制限されているものの、数年前までは立ち見や床座りの学生で、300人収容の大教室が溢れるような熱気につつまれる光景も頻繁に見られたという。
木曜日の8:30から行われる数理科学概論Ⅰは、法学部、経済学部、文学部などに進学予定の文系学生が対象である。一般に、文系学部の学生にとって、しかも早朝の数学の授業は大変そうで、敬遠されるのではないかと思いがちだ。しかし、そんな先入観をよそに学生を惹きつける小林さんの授業。そこにはいったいなにがあるのだろうか。そして、学生たちは何を受け取っているのだろうか?
この日の講義は「利率と利回り」から始まった。投資額と利率、その結果の説明に引き込まれていると、いつのまにか黒板にはピアノの鍵盤が描かれている。下のドから1 オクターブ上のドまで番号をつけ、鍵盤が12種類あるのはなぜか、と問いかける。同じ「12」でも、1年が12カ月である理由と全然違うようだ。利回りと近似とハーモニー。一見異なるものがつながっていく。普遍的な法則、それを説明しうる数学の存在が浮かび上がる。
経済、音楽、天体。それらだけではなく、巨大な数同士の比較、電車の速度を推測する方法、ハンマー投げと体格、年間の降雨量と海の水の量の比較。そんなキーワードを数学の視点で解き明かし、どのように対象を捉えるかを考え、具体的な手法に入っていく。説明に引き込まれ、数学が楽しいという意識がわき上がってくるようだ。
授業の準備には、授業時間の10倍もの時間をかけている。電車の揺れ、地形図や天気図、桜の花びら、音など、身の回りの現象や出来事の観察を通して、常に授業で取り上げる例を探し、「新作」を披露する。「学問的に新しいわけではありませんが、先生が自分で何かちょっと気づいたテーマならば、つい嬉しくなり、講義でも楽しそうに話すでしょう。そんなとき、単なる知識だけでなく、先生の思考の過程も学生さんにも伝わりやすいかな、と思うのです」。先生が楽しそう、というところがいい。
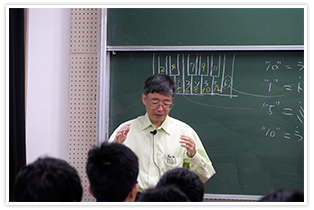 数学における定理は普遍的真理であり、それは個々の具体的事象にも何らかの形で反映されている。それを“感じとる”ことで抽象的な数学の概念の理解を深化させてほしいと考えている。逆に身の周りの現象には様々なファクターが入り込んでいるので、それを数学で説明するのは容易ではない。一つの現象の中で、何がメインで、何を切り捨てるか? その判断の根拠は? 誤差評価の授業では、「塵も積もれば山となる」ことも教える。一つの問いに対して、どのように捉え、どうやって解決し、それをどのように吟味するのか、数学的な思考力を鍛えて「基礎体力」をつけてほしい、というのがその趣旨だ。
数学における定理は普遍的真理であり、それは個々の具体的事象にも何らかの形で反映されている。それを“感じとる”ことで抽象的な数学の概念の理解を深化させてほしいと考えている。逆に身の周りの現象には様々なファクターが入り込んでいるので、それを数学で説明するのは容易ではない。一つの現象の中で、何がメインで、何を切り捨てるか? その判断の根拠は? 誤差評価の授業では、「塵も積もれば山となる」ことも教える。一つの問いに対して、どのように捉え、どうやって解決し、それをどのように吟味するのか、数学的な思考力を鍛えて「基礎体力」をつけてほしい、というのがその趣旨だ。
◎将来、必要となったときに、また勉強できる底力を育てる
 日本では、どうしても文系と理系を分けてしまいがちだが、小林さんはそのような分け方はしてほしくないという。高校で習う数学の多くの部分が300年前には完成されていた数学理論だが、学問としての数学は20世紀に爆発的に進展した。それは先端の科学・工学だけではなく、情報・金融・AIなどの世界にも用いられ、激動の時代の一つの土台となっている。しかし、現実には、法律や経済や文学を専攻する学生にとって、数学の授業はこれが最後になるかもしれない。「文系だから」と自分で言い訳して、これから先ずっと数学に壁を作って過ごすのではなく、将来、いざ必要となったときには、また勉強できるように学生時代にその素地を作っておきたい、というのが小林さんの願いだ。小林さんの友人が教鞭をとっていたシカゴ大学では、経済学部の学生は、線型代数だけでも週3コマの授業と毎週の宿題があるという。一方の東大は1コマ。世界のスタンダードから離れていくことを心配している。そして、使命感に似た気持ちで、東大の文系1・2年生を対象とする数学の講義を自らが率先して担当することを決意したという。
日本では、どうしても文系と理系を分けてしまいがちだが、小林さんはそのような分け方はしてほしくないという。高校で習う数学の多くの部分が300年前には完成されていた数学理論だが、学問としての数学は20世紀に爆発的に進展した。それは先端の科学・工学だけではなく、情報・金融・AIなどの世界にも用いられ、激動の時代の一つの土台となっている。しかし、現実には、法律や経済や文学を専攻する学生にとって、数学の授業はこれが最後になるかもしれない。「文系だから」と自分で言い訳して、これから先ずっと数学に壁を作って過ごすのではなく、将来、いざ必要となったときには、また勉強できるように学生時代にその素地を作っておきたい、というのが小林さんの願いだ。小林さんの友人が教鞭をとっていたシカゴ大学では、経済学部の学生は、線型代数だけでも週3コマの授業と毎週の宿題があるという。一方の東大は1コマ。世界のスタンダードから離れていくことを心配している。そして、使命感に似た気持ちで、東大の文系1・2年生を対象とする数学の講義を自らが率先して担当することを決意したという。
 数学の理論は強力であるが、無理に社会現象に当てはめれば、意味のない数値が出現し、正しい判断の妨げになりうる。また、「公式はブラックボックスにすると危険」とも。公式に頼ると思考が停止することもありうるというのである。原理を見抜くプロセスをスキップしてしまうようなことはしてほしくない。数学的な思考力は、厳密な論理と大らかな感覚の両方から磨いてほしい、と考えている。たとえば、山の斜面の傾斜。あるいは、日本全体に1年間に降った雨の体積。インターネットなどを見ないで、自分の経験と知識と思考を総動員して、短時間で見積もってみる。多少の誤差は構わないが「桁違い」にならない推定を目指す。あやふやな知識に頼った部分があれば、大きな誤差につながる。解法は何通りもあるだろう。データがあやふやだと気付けば、別のアプローチに切り替える。こういったトレーニングをすることで、自分で考え、自分で判断し、吟味する、数学的な能力を磨くのに役立つだろう。同時に、偏微分や多重積分に関する普遍的な理論が、何を意味しているのか、それぞれの学生の胸に刻みつけられることになる。頭が柔らかい若いうちに思考力を磨き、難しく抽象的な数学概念を扱うコツを会得しておけば、将来、いざ必要となったときに、また勉強できる素地になる。
数学の理論は強力であるが、無理に社会現象に当てはめれば、意味のない数値が出現し、正しい判断の妨げになりうる。また、「公式はブラックボックスにすると危険」とも。公式に頼ると思考が停止することもありうるというのである。原理を見抜くプロセスをスキップしてしまうようなことはしてほしくない。数学的な思考力は、厳密な論理と大らかな感覚の両方から磨いてほしい、と考えている。たとえば、山の斜面の傾斜。あるいは、日本全体に1年間に降った雨の体積。インターネットなどを見ないで、自分の経験と知識と思考を総動員して、短時間で見積もってみる。多少の誤差は構わないが「桁違い」にならない推定を目指す。あやふやな知識に頼った部分があれば、大きな誤差につながる。解法は何通りもあるだろう。データがあやふやだと気付けば、別のアプローチに切り替える。こういったトレーニングをすることで、自分で考え、自分で判断し、吟味する、数学的な能力を磨くのに役立つだろう。同時に、偏微分や多重積分に関する普遍的な理論が、何を意味しているのか、それぞれの学生の胸に刻みつけられることになる。頭が柔らかい若いうちに思考力を磨き、難しく抽象的な数学概念を扱うコツを会得しておけば、将来、いざ必要となったときに、また勉強できる素地になる。
学生時代には、専攻以外の学問がどのような場面で必要になるのか、具体的にイメージするのはなかなか難しい。しかし、仕事をしてみると、専攻以外の科目であっても「あれを知っていたら、少しでも分かっていたら活用できるのではないか」と思う場面はある。「いざ、必要になったときに、新しいことを勉強できるための力を若いうちに育んでほしい」。この「勉強」という言葉のなかに、数学が社会の中で活用される場面が見えてくる。この授業は、そんな小林さんの意図を真正面から受け止めた学生とともに作られているようだ。
◎すべての教員が、授業に力を注ぐためには? と問いかけてみた
研究者にとって、論文執筆、学会発表は重要な仕事だ。業績として評価され、また社会や研究機関もそれを期待している。一方、教育活動も次世代を育てる重要な仕事である。しかしながら、論文や学会発表などのように成果を見極めにくく教育活動についての評価の基準も定めにくい。そのため、第一線の研究者でもある大学の教員が教育活動に注力することが実質的に難しい状況を生み出している環境があることも否めない。
多くの大学教員が、教育に注力できるようになるためにはどうしたらいいのだろうか? と小林さんに尋ねてみた。「すべての先生が、エネルギーを教育活動に注ぎ、熱心に分かりやすく教えるのが善であるというバイアスをかけるのは、むしろ危険ではないでしょうか。それこそ、大学教育に短期的かつ画一的な成果を求めるようになってしまう。もっと大らかに考えたいですね。命を懸けて何かに取り組んでいる先生が、オーラを発しているけれども、講義が分かりにくい、とか、いやいやながら講義をしているようにみえる、というようなことがあってもいいと思うのです」。
各分野で傑出した教員が、それぞれにもっている雰囲気、考え方、姿勢。その中から他では得難いものを学び取れるかもしれない。高校までの教育であれば一定の到達点の共有が大事だとしても、大学では、バラエティに富んだ教員から知識以上のものを学んで逞しく成長してほしい、と小林さんは語る。「大学は長期的な視点で、人材を育てる責務があります。どんな人材を育成したいか、そのために自分は何ができるか、ということも教員によって考えが違うでしょうし、同じ教員でも年齢と共に考えが変わっていくかもしれません。バラエティに富み、そして何かに傑出した教員たちが自己の経験と思索から、それぞれの見識を形成することが大学の底力となるでしょう」。
 今の学生が社会に出て活躍するこれから数十年間に、時代が激動する。どのように時代が変化しても、それに正面から対峙して合理的な判断をする。そのための素地として、本物の教養と知性と地力を育てることが、大学の教育の使命の一つだと小林さんは考える。
今の学生が社会に出て活躍するこれから数十年間に、時代が激動する。どのように時代が変化しても、それに正面から対峙して合理的な判断をする。そのための素地として、本物の教養と知性と地力を育てることが、大学の教育の使命の一つだと小林さんは考える。






