北海道から九州に至る日本の広い範囲に分布し、春になるとびゅんと伸びた茎の先に小さな白い花をつける「シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana) 」。アブラナ科に属するこの小さな植物は、ゲノムサイズが小さいなどいくつかの特徴から、近年、生物学の実証研究に欠かせない「モデル生物」として大きな注目を集めてきた。このシロイヌナズナを使って、植物の形態形成メカニズムのキーとなる遺伝子のいくつかを、世界に先駆けて発見してきた東京大学大学院理学系研究科 塚谷裕一教授。「植物調査などが趣味」という稀代の博学に加え、分子遺伝学的知見を元に幅広い研究手法を駆使する研究室に、塚谷教授を訪ねた。
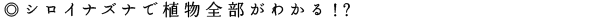
 私たちの研究室では、葉っぱの形態形成を研究しています。葉、茎といった植物の基本パーツの研究が進んできたので、その応用として、それをどう変化させているのか、というそのしくみも取り扱えるようになった。そこで、植物が環境に適応してさまざまな葉を発生させることができる「可塑性」にも注目しつつ、分子レベルでの解明を進めています。また発生を遺伝子の発現調節から考える新しい潮流である「発生進化生物学(Evolutionary Developmental Biology, エボデボ)」的な研究にも取り組んでいます。
私たちの研究室では、葉っぱの形態形成を研究しています。葉、茎といった植物の基本パーツの研究が進んできたので、その応用として、それをどう変化させているのか、というそのしくみも取り扱えるようになった。そこで、植物が環境に適応してさまざまな葉を発生させることができる「可塑性」にも注目しつつ、分子レベルでの解明を進めています。また発生を遺伝子の発現調節から考える新しい潮流である「発生進化生物学(Evolutionary Developmental Biology, エボデボ)」的な研究にも取り組んでいます。
研究室では大きく、シロイナズナを使っている人とそうでない人がいます──大まかに言って、シロイナズナのほうは被子植物に共通なメカニズムの解明を、そうでないほうは研究対象にしている植物種に固有の現象を追究しています。ただ共通メカニズムという言葉には注意書きが必要です。私はフィールド調査も好きなので、野外でいろいろな植物を見てきました。そうした立場からすると、シロイナズナと完全に共通の仕組みを持つのは、被子植物のごく狭い範囲であるに違いないと思っています。植物の研究者の多くはたぶん、シロイナズナを解明できれば植物全部がわかると考えているだろうと思いますが、私は例外ばかりだろうと思う。そのくらい植物は多様であり、世の中にはたくさんのバリエーションがあります。
そもそも人々の関心には刹那的なところがあって、ちょっと前までとても流行ったものでも、しばらくするとすっかり忘れられてしまうことがよくあります。シロイナズナも、私が大学院生の頃まではほとんど誰も知らなかったのに、今や植物学者なら誰でも知っていないとおかしいくらいのものになっている。ただシロイナズナの国際会議は最近、年々、参加人数が減ってきており、技術の発達のおかげで、シロイナズナでなくても自分の好きな材料で好きな問題をやればいいという潮流へと戻りつつあります。2世代ぐらい経ったら、もしかしたら「シロイナズナって何?」という時代になるかもしれません。

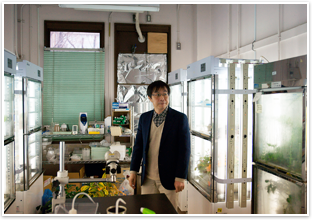 生物の本質のひとつは、多様性であると考えます。それに対して物理学の場合は、極言すれば、それは統一原理を追究しているのでしょう。ところが生物学はケース・バイ・ケースです。全部の生物に共通の原理があると思っている人も中にはいるでしょうけれど、そんな原理はたぶんない。本質的に個別論であって、ですから森羅万象として記述されるべきものはすごく多いわけです。極限における1個の数式が見つかれば、あとの全部が辿れるという考え方とは、だいぶ違います。
生物の本質のひとつは、多様性であると考えます。それに対して物理学の場合は、極言すれば、それは統一原理を追究しているのでしょう。ところが生物学はケース・バイ・ケースです。全部の生物に共通の原理があると思っている人も中にはいるでしょうけれど、そんな原理はたぶんない。本質的に個別論であって、ですから森羅万象として記述されるべきものはすごく多いわけです。極限における1個の数式が見つかれば、あとの全部が辿れるという考え方とは、だいぶ違います。
ジャック・モノー(Jacques Lucien Monod、1910 - 1976)の時代は、大腸菌で真なことはゾウでも真であるということが言われた。そこで大腸菌が盛んに研究されたわけですが、やがて大腸菌では真核生物を解明できないことがわかって、その後は研究材料として酵母が大いに流行りました。しかし酵母だけではやはり真核生物すべてをカバーできない。当時は無名に等しかったシロイヌナズナですが、今や年間論文数でいって、酵母とシロイナズナはほとんど同じです。このように何かひとつの材料で生物の全てがわかるという考えは、とうの昔に破綻しています。ある特定の生物のことを知りたければ、基本的にその生物を調べるしかないのです。
ただし生物全てに共通しているものも確かにあります。たとえば遺伝子の塩基配列などは、もちろん大腸菌を調べれば十分です。また動物と植物とは明治以来、別々に扱われてきましたが、遺伝子やタンパク質で見る限り、互いによく似たものを使っていることが分かってきています。このように言葉が共通化したのは、分子生物学の大きな貢献と言えるでしょう。一方、分子遺伝学が研究手法として広く使われるようになってからは、扱っている遺伝子やタンパク質の系統樹をかく習慣が一般化しました。この系統樹というものは進化の概念そのものですね。個別論を扱いつつも、それが進化の筋道の大きな流れの中にあるという世界観をきちんと踏まえている。ちなみに最近の若い学生や研究者には、「進化なくして生物学なし」という昔の言葉を引用する人が増えてきたな、と感じています。

 一方、フィールド調査の醍醐味は、やはり新種の発見でしょう。ボルネオでの調査の例でお話しすると、バルボフィラムという蘭の一属の新種を見つけたことがあります。このとき、採取はしたものの、実はずっと同定を後回しにしていました。なぜならバルボフィラム属は、蘭の中でたぶん最大に近い属で、世界中に500種類以上もいるんです。新種かどうか判断するには、500種類を全部調べて、そのどれでもないことを確かめないとならない。それは大変なので、まずDNAを読んでみました。そうすると500種のうちどのグループに近いかがわかるので、それで50種ぐらいに絞り、さらに自生地から30ぐらいに絞った。その30種類を全部確かめて、やっと新種であることがわかりました。
一方、フィールド調査の醍醐味は、やはり新種の発見でしょう。ボルネオでの調査の例でお話しすると、バルボフィラムという蘭の一属の新種を見つけたことがあります。このとき、採取はしたものの、実はずっと同定を後回しにしていました。なぜならバルボフィラム属は、蘭の中でたぶん最大に近い属で、世界中に500種類以上もいるんです。新種かどうか判断するには、500種類を全部調べて、そのどれでもないことを確かめないとならない。それは大変なので、まずDNAを読んでみました。そうすると500種のうちどのグループに近いかがわかるので、それで50種ぐらいに絞り、さらに自生地から30ぐらいに絞った。その30種類を全部確かめて、やっと新種であることがわかりました。
ボルネオのような熱帯雨林の場合、林の一角に立ったとき、そこで目に入るすべての植物の名前がわかるという人は、世界中に1人もいないはずです。自分の守備範囲のグループならわかるという人しかいない。その上熱帯では、講義で必ず教えるような「植物はこのような規則で形をつくっていますよ」といった基本ルールを逸脱している植物が、いっぱいいる。温帯のおとなしい植物たちに比べて、熱帯の植物は非常に多様であり、あらゆる面についていろいろな応用を試みている。これでは例外が多すぎて、ルールが見つけられないでしょう。もし熱帯で文明が勃興していたら、生物学はまだまだプリミティブで、何が基本で何が応用なのか、全然わからなかったでしょう。かねてから、近代生物学は温帯だからこそ成立したんだと、思っています(笑)。






