人の何倍もの力を持ち、瞬時に計算をこなして、高速で作動し、求められた通りの成果を出す。どこまでも正確に、どこまでも緻密に、どこまでも人間に近く……。そんな、ロボットのイメージとは正反対のロボットたちが「いる」。たどたどしく話し思わず助けてあげたくなる、役に立たないのに近くにいないとなんだか寂しい。そんな「弱いロボット」に取り組んでいるのは、豊橋技術科学大学の岡田美智男教授だ。ロボットとはなんなのか? 人はロボットと関わることでなにを得ようとしているのか? researchmap開発者の新井紀子教授が、弱いロボットの奥底にある意味を探る。
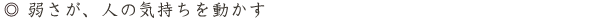
出迎えてくれたのは、岡田教授の研究室で生み出されたロボットたちだ。ゆらゆらとおぼつかない動きで近づいてくる〈ゴミ箱ロボット〉は、ゴミを見つけて近寄るものの拾うことはできない。人に近づいてペコと頭を下げるしぐさをする。ゴミを拾って入れてもらうと、またペコリ。「お願いします」も「ありがとう」の言葉もない。人はなぜ、ゴミを拾ってあげたくなるのだろうか。
新井:ゴミを入れたとき、「ありがとう」と言わせることは技術的には簡単にできますが、あえて言わせないことを選択しているのはなぜなのでしょうか。
岡田:直接的な言葉ではなく、身体を備えることで可能となるコミュニケーションがあると思うのです。その仕組みを明らかにしたいということが一つあります。それと、私たちがモノを作るとき、なんの役に立つのかを評価の指標にすると、作り手はその指標に向かって最適化しようとしてしまいます。そして、その目的からほんのちょっとでもずれると、それは役に立たないモノになってしまう。それはなんだかイヤだなと思うのです。
新井:学会などでは「ありがとうと言わせた方がゴミはもっと集まるのではないか?」といった意見が出ると思うのですが、「イヤ、それはちょっと違う」とお考えになる背景にはそのように成果を測ろうとすることに抵抗する気持ちがおありなのですか。
岡田:ゴミ箱ロボットは、なんだか頼りないしゴミを見つけても自分で拾うことはできません。つまり、周囲をきれいにするという目的に対して最適ではありません。でも、周りの人が助けてあげたいな、ゴミを入れてあげたいなという気持ちになる。そういう関係性の中で、ロボットの役割や機能が自然に立ち現れてきてもいいと思うのです。そうした場は人の優しさや共同性を引き出すものでもあるんですね。
新井:たとえば、お年寄りにロボットを持ってもらうとしますね。ロボットと「対話」することで発話が増えるとか認知症が改善するというように、ある目的に対してどんな結果が出たかということは、結局は数理モデルありきで、それでしか切り取ることができない。でも、そのような評価の軸で測れないことはたくさんあります。数理モデルを使った手法でこぼれ落ちてしまうことに、どんなことがあるとお考えですか。
 岡田:たとえば、私たちの身体と相手の身体との間に生まれる関係性や場のようなものは、なかなか数理モデルにはのりにくいなぁと思っています。形式化を急ぎすぎたり、ある要素だけを取り出し抽象化している間に、もっとも大切なことがいつの間にかこぼれ落ちていたりする。それと、そもそもお年寄りがそうしたことを本当に望んでいるのかどうか。私が大学時代にお世話になった先生は、「鳥で行くか、飛行機で行くか」でいえば「鳥で行く」という考え方をする人でした。金属板にジェットエンジンをつけて飛ぶことはできますが、鳥の微妙な羽ばたきを見ながら空を飛んでみたいということもあるでしょう。ジェット機の方が速くて便利なのだからといって鳥よりも優れていると言えるのか。今の情報科学は、力尽でなんでもやってしまっているようで、それもイヤなんです。
岡田:たとえば、私たちの身体と相手の身体との間に生まれる関係性や場のようなものは、なかなか数理モデルにはのりにくいなぁと思っています。形式化を急ぎすぎたり、ある要素だけを取り出し抽象化している間に、もっとも大切なことがいつの間にかこぼれ落ちていたりする。それと、そもそもお年寄りがそうしたことを本当に望んでいるのかどうか。私が大学時代にお世話になった先生は、「鳥で行くか、飛行機で行くか」でいえば「鳥で行く」という考え方をする人でした。金属板にジェットエンジンをつけて飛ぶことはできますが、鳥の微妙な羽ばたきを見ながら空を飛んでみたいということもあるでしょう。ジェット機の方が速くて便利なのだからといって鳥よりも優れていると言えるのか。今の情報科学は、力尽でなんでもやってしまっているようで、それもイヤなんです。
新井:一部の要素を目的化して性能や機能を付加し、その競争が起こる。しかしその行き着く先に、本当に必要なもの、大切なものが生まれるのだろうかという疑問ですね。
岡田:個体の中に機能をすべて帰属させようとするのが、これまでの性能競争ですね。でも、それだけじゃないと思うのです。ロボットの個体がもつ機能ですべての成果を出すのではなく、周囲と一緒に何かをするという機能もあるでしょう。ゴミ箱ロボットは、近くにいる人に「ゴミを入れてあげたいな」という気持ちを起こさせます。人は手をさしのべてゴミ箱を助けることになる。そこに関係が生まれる。そういう側面をロボットを使って研究できるのではないかと思っているのです。
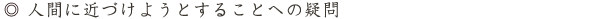
 たどたどしく話す〈む〜〉。軟らかい曲線としっとりとした質感の体。その真ん中に、大きな目玉が一つ。話しかけながら、大きな目を思わず見つめてしまう。プルルンと体を揺すって話すものの、話し方は幼児のようなたどたどしくおぼつかないものだ。言葉も聞きづらく、「え? もういちど言って」と顔を近づけてしまう。
たどたどしく話す〈む〜〉。軟らかい曲線としっとりとした質感の体。その真ん中に、大きな目玉が一つ。話しかけながら、大きな目を思わず見つめてしまう。プルルンと体を揺すって話すものの、話し方は幼児のようなたどたどしくおぼつかないものだ。言葉も聞きづらく、「え? もういちど言って」と顔を近づけてしまう。
新井:む〜の話し方は、文節の区切りも正しくないし、なんだかとてももどかしいですね。
岡田:このたどたどしさにも価値があるんです。思わず聞き耳を立てたり、その会話に参加してみようという気持ちになったり。たどたどしさは、そうなるための財産だと思うんですよ。
新井:む〜と話していると、つい聞いてしまうし、言っていることを理解しようと気持ちになります。
岡田:工場や倉庫、病院などで、人の仕事を肩代わりさせて効率的に作業をすることが目的なら、最適化するのは分かります。しかし、ロボットにどんどん新たな機能を追加して、完全なものに近づけようとすればするほど、それは完成度の高い機械にはなるけれど、むしろ「人らしさ」からは遠ざかってしまうように思うのです。
新井:私も、モノに機能をどんどん付け加えていくような、わけのわからないインクリメンタルな世界をどうしたら止めることができるのかと思っています。そうしないと、定量化できない軸は消え去るしかなくなってしまいます。定量的な評価の必要性などを指摘されることもありますが、「これでいい」ということの根拠や妥当性をどう示すことができるのか。それを知りたいと思うのです。
岡田:どうすればいいんでしょうね。関係性の質とか、それがどのようなものを生み出すのか、そういう余白とか、なにか新たな指標が必要なのかもしれません。それは目に見える機能として、すぐに役に立たつかどうかじゃないんですね。そういう意味では、このむ〜はまだちょっとしゃべりすぎかなと思っているんです。
新井:これでも、しゃべりすぎと思われるんですか。
岡田:自動販売機が「ありがとうございました」と言いますよね。あれは非常に違和感がある。この機械は、言葉の意味をまだ分かっていないのに「ありがとう」と言っていると。私は、以前は音声の研究をしていましたので、最初にこの合成音を耳にしたとき「ああ、すごい時代になったものだ」思ったし関心を持ちました。でも何度か聞いているうちに、お礼の気持ちとして伝わってこないじゃないかと思うようになったんです。自分の言葉として話していないのがイヤで、それならまだ言葉はなくてもいいのではないかと考えるようになったのです。心もないのにロボットがしゃべり、何でも解決できるとするのは、なんだかおこがましいですよね。
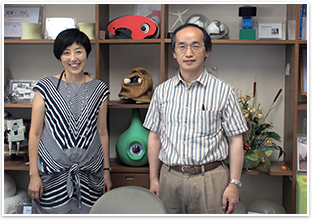 新井:技術的にできるからといって、次から次へと機能を付加していく先に、なにがあるのかと。
新井:技術的にできるからといって、次から次へと機能を付加していく先に、なにがあるのかと。
岡田:ロボットの機能が増えれば、僕らはさらに要求水準を高めてしまいます。もっと速く、もっときれいに、もっと静かにできないのか、と。今までのロボット作りは「足し算」で、それはこの個体の中に機能を詰め込んでいることにほかならない。量販店などに行くと、毎年毎年、新しい製品が出て機能が増えていく。なぜそうなるかというと、同じ値段なら消費者は機能の多い方を買うからで、技術者はどんどん新たな機能を追加していくわけです。ドナルド・ノーマン(*)は「なし崩しの機能追加主義」と呼んでいます。モノづくりの現場から考えると、それでは消耗戦になってしまう。
*アメリカの認知科学者、認知工学者
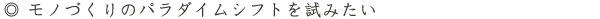
 ゆらゆらと揺れながら、近くを動き回る〈ペラット〉。倒立振子の振る舞いによって、ふらふらとした動きで近づいてくる。が、なにもせずそこにいるだけだ。でも離れていくと何となくさみしい。弱いロボットは、ロボットの世界にとどまらない大切な問いかけを含んでいるのではないだろうか?
ゆらゆらと揺れながら、近くを動き回る〈ペラット〉。倒立振子の振る舞いによって、ふらふらとした動きで近づいてくる。が、なにもせずそこにいるだけだ。でも離れていくと何となくさみしい。弱いロボットは、ロボットの世界にとどまらない大切な問いかけを含んでいるのではないだろうか?
新井:む〜を商品化しませんか? という依頼が来たら、どうしますか?
岡田:うーん、む〜をあまり外に出したくないという気持ちは正直ありますね。
新井:もし私が年をとって友達も話し相手もいない暮らしのなかでむ~に話しかけていたとすると、それは寂しすぎる光景で、そういうことはお嫌なんですね? そんなふうにむ〜が使われても、私にとって幸せではないだろうと。
岡田:そうですね(笑)。ロボットと人とが1対1で会話している姿って、なぜだか痛々しいんです。でも、何人かいてむ〜がいるという状況なら、そこにコミュニケーションが生まれます。
あるとき、こんなことがありました。桜の咲く公園でひとりのおばあちゃんがぽつんと立っていたのです。そして、小さなぬいぐるみのロボットを抱っこしながら「きれいだねぇ、ねぇ、きれい、きれい」と桜を見ながら語りかけていたのです。その姿を見て、ロボット研究者として申し訳ないことをしてしまっているのではないかと、いたたまれない気持ちになってしまって。なにかとても痛々しいものを作っているのではないかと感じたのです。そのまま突き進んだら、「おばあちゃんをどう欺くか」という研究になってしまわないかと。
新井:ペラットは、ゆらゆらとそばに寄ってくるだけで、なんの役にも立ちません。でも、ペラットがいることで、何かを生み出すかもしれない。
岡田:役に立たないものでも大切なものがあるんですよね。そういうことをロボットが生み出すこともできるんじゃないかと思っているんです。
新井:私は数学科出身だからよく理解できないんですが、工学部では「役に立つ」はまさにレゾンデートルで、そこを否定したら大変なことになってしまう。にもかかわらず、「役に立つ」ということだけが大切なのか? という問いが人文系ではなく工学部から出てくるということは、とても大切だと思います。現在は、能力が要求に達しないという理由で役に立たないとされ、人を切り捨てるようなことも起こります。しかし、その人は評価の軸に乗らないけれども、コミュニティやその場に対して大切な役割を果たしているかもしれませんね。その人がいてこそのコミュニティだったということがあります。
岡田:私は、能力給が導入されたあたりから、日本の企業が元気がなくなってきたのではないかと感じているんです。本当はチームとして力を発揮するのに、個人としての能力を問うだけになっている。大学の教員に対しても偏った物差しだけで測られてしまうというのはありますね。
新井:学生の教育なども含めて考えますと、成果や業績の表し方は難しいですね。大学は人を育てる場のはずなのに、論文を本数や引用数など数値で計測できるものによって測りましょうとなったときに、大切なことがすっぽりと抜け落ちる。それでは、学問も研究もどんどんやせ細ってしまうのではないかと思います。
岡田:どうしたらいいでしょうね。工学部で、役に立つことにあまり関心がないというのは、あまのじゃくかもしれないんですけど、役に立たないけれども大事なところはあるわけで、そこをていねいに見ていきたいと思っているんです。






