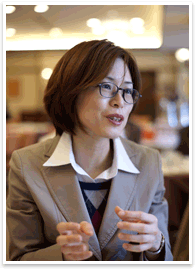 そもそも西洋の研究は伝統的に、言葉(とそれが持つ概念性)にすごくこだわりを持つわけですが、「有用性(utilité)」や英語の「utlity」という語も、欧米語においてはインデックス(指標)となる役割を担っています。単に役立つという現世的な有用性だけでなく、「公共善(公共の福祉)」を追求する、あるいは貢献するといった意味の、精神的な次元を多く含む言葉なんですね。
そもそも西洋の研究は伝統的に、言葉(とそれが持つ概念性)にすごくこだわりを持つわけですが、「有用性(utilité)」や英語の「utlity」という語も、欧米語においてはインデックス(指標)となる役割を担っています。単に役立つという現世的な有用性だけでなく、「公共善(公共の福祉)」を追求する、あるいは貢献するといった意味の、精神的な次元を多く含む言葉なんですね。
語はラテン語のutilitasに遡り、共同体の福祉に関わる概念です。たとえば「文化が発展するのは都市の栄光に有用である」といったふうに用いられます。古代ローマのキケロがレトリック(修辞学)の説明のなかでも、採り上げたりしています。
また学問の有用性ということでは、「なぜこの学問をやるのか?」というのは大事なトピックで、中世以来のヨーロッパの大学ではしばしば最初の講義に提示されたそうです。ルネサンス以降だと「なぜ数学を学ぶのか?」ということも論じられたりしました。
またフランスでは17世紀、公共善という概念は、主に王の言葉としてある──つまり、神から任務を負った国王が、国父として、自分の臣民のために尽くす、それが「公共善」の意味するところでした。それが18世紀後半になると国家そのものではなく、政治的にも経済的にも半ば自律した市民社会という概念が漠然と捉えられるようになり、「公共善」もその市民社会にとっての福祉を意味する語彙として使われるようになっていきます。
そして19世紀、次第に科学が勢いを持ち始めると、科学の基礎研究は「有用」である、科学の発展に役立つからだ、といった言い方がなされるようになっていきます。いわば科学の価値がその外の世界とは離れて自律的になってくる。たとえば化学者のラヴォアジエ(Antoine-Laurent de Lavoisier, 1743-1794)の頃に、既になぜこの研究が必要なのかをあまり説明しない論文が増えているんです。
ところで私が「有用性」という言葉について考えようと思ったひとつのきっかけは、実は、フーコーなんです。科学アカデミーの文献をひもといた時、フーコーという思想家が触れていた「有用性」という主題が、きれいに浮かび上がってきた!──その時のことを、よく憶えています。
 |
|
中山 元
筑摩書房 1996年6月 ISBN-13: 978-4480056719 |






