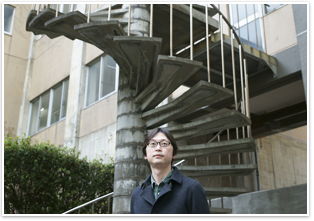 哲学の目的とは何か?──たとえば「人生の意味はこれです」と実際に答えを与えるというのは、もちろん哲学の仕事ではありません。それはおそらくは宗教の仕事でしょう。この問いは人間にとって非常に重要だし、個々人が自分なりの答えを見つけることは十分あり得ます。哲学は、そのように直接答えを与えるのではなく、むしろ「人生の意味とは何か」という問いがどういう問いであるのかを整理し、そのポイントを明確にするといった仕方で、こうした問題を取り扱うのだと言えるでしょう。
哲学の目的とは何か?──たとえば「人生の意味はこれです」と実際に答えを与えるというのは、もちろん哲学の仕事ではありません。それはおそらくは宗教の仕事でしょう。この問いは人間にとって非常に重要だし、個々人が自分なりの答えを見つけることは十分あり得ます。哲学は、そのように直接答えを与えるのではなく、むしろ「人生の意味とは何か」という問いがどういう問いであるのかを整理し、そのポイントを明確にするといった仕方で、こうした問題を取り扱うのだと言えるでしょう。
だから、その取り扱い方自体がまさに哲学者ひとりひとりの腕の見せどころであって、古典と言われるものは、その人ならではの魅力的な取り扱い方を作り出したものと考えることができます。たとえば「人生の意味」という問いであれば、人々の多くはこの問いの前にただ途方に暮れて、呆然と佇んでしまう。そのうちの幾人かが古典の議論によって導かれ、手掛かりにしたり、補助線を得たりする。あるいは、同じように問いを持っていた人が、その扱い方に反発して別の議論を始めたりする。個々の問いを巡るそうしたさまざまな議論の歴史が哲学的な思考の系譜を基本的に形作っているし、現代に生きる私たちがその歴史をたどって思考を追体験することも、すぐれて哲学の営みの一部だと思います。
けれども、ひとがそのように哲学できるのは、まだ自分で額に汗して考える元気が少しでもあるときというか、心に強さが残っているときであって、実生活で心底打ちひしがれてしまった場合には、哲学は役に立たないようにも思います。「人生の意味」という言葉が全く空虚になるほどの苦難に直面して、立ち直れないほどつらい状況では、筋道立った思考を続けることはとてもできないのではないか。そのときに必要なのは、むしろ休らうこと、眠ること、それを提供する場所でしょう。
哲学は、子守歌を聞かせるものではなく、逆に鼓舞するものであり、私たちを眠り込ませず、うっとりとしつつあるその目を開かせようとします。うっとりと物事を眺める固定された視点に私たちが囚われそうになっているときに、そことは別の角度から見つめ直すように、哲学は促す。それは、哲学がもつ苛烈さでもありますが、同時に、哲学の積極的な役割もそこに見出すことができます。それは一種の「予防」的な役割と言ったらいいんでしょうか。悲劇に打ちのめされ、ほんとうに立ち上がれなくなってしまったら、確かに、もう眠り込むことしかできないでしょう。そうなる前に、その手前で、悲劇に立ち向かうための強さを、哲学は各人のなかに生み出し育んでくれる。それは、ままならない世界であっても、それを自分の目で見つめ、自分の言葉で掴もうとする力です。そして、その力を身につけておくためには、悲劇に襲われる前に、やはり普段から哲学に触れている必要があるし、哲学者のように四六時中やっている必要はありませんが(笑)、時折でも「自分で哲学する」という経験をしておくことが肝心だと思います。






