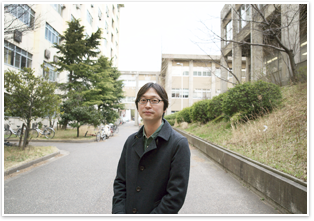 哲学の場合、もちろんいろんな立場の人がいるわけですが、たとえば脳のメカニズムを解明するといった目標があらかじめ設定されていて、それに資するような結論を出さなければいけないというのとは、ちょっと違うと思うんです。特定の病気を治そうとしているわけでもなければ、なんらかの新現象を発見しようとしているのでもない。そのような意味での目的が哲学にあるわけではないので、結果として出てきた結論が科学的な説明と整合しないからといって、それを手放す必要もないし、現代の常識からみて変な結論が出てきたとしても、言い方は悪いですが、別に気にしない。
哲学の場合、もちろんいろんな立場の人がいるわけですが、たとえば脳のメカニズムを解明するといった目標があらかじめ設定されていて、それに資するような結論を出さなければいけないというのとは、ちょっと違うと思うんです。特定の病気を治そうとしているわけでもなければ、なんらかの新現象を発見しようとしているのでもない。そのような意味での目的が哲学にあるわけではないので、結果として出てきた結論が科学的な説明と整合しないからといって、それを手放す必要もないし、現代の常識からみて変な結論が出てきたとしても、言い方は悪いですが、別に気にしない。
むしろ、きちんと論理的に導き出された結論であれば、それは「常識」に押し流されないタフな議論だと言うことができます。そして学問の内部で意味を持つ議論であれば、それは客観的な正しさを持っているはずです。ただし、そうやって学問的な議論を積み重ねて行った先には、完全に客観的な視点には回収されない微妙な領域というものも出てきます。今回の本も最後はそこに踏み込んでいったわけですが、ともあれ、その領域を捉えるためにも、考え切れるところ、明晰にできるところまでは、整理していかなければなりません。
一番つまらないのは、汗をかかないタイプの議論です。手の内のカードを見せず、自分が攻撃を受けないどこまでも優位な立場から、飾り立てた言葉で煙に巻くだけの議論。そうではなく、哲学にはやはり、問題を解こうと愚直にもがく泥臭い部分、いわばドン・キホーテ的な部分もなければいけない。ウィトゲンシュタインの比喩に、「哲学とはもつれた糸をときほぐすことのようなものだ」というのがあるんですが、たしかにそういう感じがします。目の前にはもつれた糸(哲学の問題)がいろいろある。そのひとつが気になって手にとってしまったら、焦ってどこかをぴゅーっと引っ張ったりせずに、さまざまな方向から頑張ってじんわりほぐして、これでやっとほどけたというところへいこうと汗をかく。もっとも、その問題を自分で最後までほぐせるかどうかはわからないし、そもそも誰もほぐせる問題ではないかもしれない。たとえそうだとしても、そのことを知るためにはとにかく、ほぐそうと思わないとだめなんですね。
哲学では、ありとあらゆることがテーマになり得るし、それぞれのテーマはゆるやかにつながっています。その人の能力の及ぶ範囲で、あらゆることを考える。哲学は泥臭くあらねば、と言いましたが、その地道な営みは、世界をあるがままに捉えたいという、ある意味で法外な野心によって支えられている。その身の丈に合わない野心に導かれて、頭を振り絞って悩みながら、たまには楽しみながら、目の前に現れる問題に対して一歩一歩、よしこれでほどけたっていう、そのつどの真理に辿り着こうとしているんですね。






