社会から研究課題を抽出するには? 研究を社会に実装するには? 農産物の光害と夜の町の安全・安心の両立のために、大学は何ができるのだろうか。地域に実装するにはどのようなスキームが必要なのだろうか? 社会課題、大学、そして大学発ベンチャーのあり方を、光害抑制照明の研究から考える。
◎経験に基づく研究者の気づき
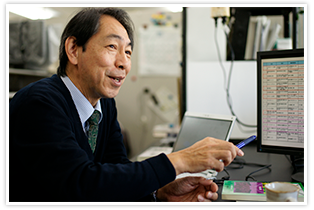 夜道が明るい。防犯の観点からは、夜間に街路や公園、公共スペースが明るいのは望ましいことのように思える。しかし、夜は暗くなるのが自然なこと。本来暗い状態があたりまえの環境に照明を取り付け、人の手によって明るさを保つことで「光害(ひかりがい)」の問題が発生する。一般に、光害というと町中の灯りや商業施設が発するサーチライトなどが原因で、星空が見えないなどの弊害をイメージする人が多い。実際、長崎県ではサーチライトが不用意に夜空を照らすことなどを規制した「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」のなかで、「サーチライトなどは特定の対象物を照射する以外の目的に使用してはならない」と定めている。しかし、植物の生育、農業生産にも弊害があることはあまり知られていない。明るいことが及ぼす負の影響の範囲は意外に広いのである。
夜道が明るい。防犯の観点からは、夜間に街路や公園、公共スペースが明るいのは望ましいことのように思える。しかし、夜は暗くなるのが自然なこと。本来暗い状態があたりまえの環境に照明を取り付け、人の手によって明るさを保つことで「光害(ひかりがい)」の問題が発生する。一般に、光害というと町中の灯りや商業施設が発するサーチライトなどが原因で、星空が見えないなどの弊害をイメージする人が多い。実際、長崎県ではサーチライトが不用意に夜空を照らすことなどを規制した「長崎県未来につながる環境を守り育てる条例」のなかで、「サーチライトなどは特定の対象物を照射する以外の目的に使用してはならない」と定めている。しかし、植物の生育、農業生産にも弊害があることはあまり知られていない。明るいことが及ぼす負の影響の範囲は意外に広いのである。
 光害については環境省も対策を進めている。同省が定めた「光害対策ガイドライン(平成18年12月改訂)」では、「光害とは、良好な『光環境』の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、又はそれによる悪影響」と定義。想定されている光害の影響範囲は、昆虫も含めた動物や植物、生態系、農作物や家畜など多岐にわたる。人への影響も、よく知られた天体観測だけではなく屋外照明の光が住居内に差し込むことによる安眠の妨げやプライバシーの侵害、不適切な街路灯などの選定により歩行者が不快なまぶしさを感じるといった内容も含まれる。都市部では、深夜まで営業する商業施設の明るい看板が住宅と近接している事例も少なくない。光害の問題は予想以上に深刻だ。自動車、船舶などの運行における標識や危険物察知などの視認性も、光害が及ぼす影響として想定されている。
光害については環境省も対策を進めている。同省が定めた「光害対策ガイドライン(平成18年12月改訂)」では、「光害とは、良好な『光環境』の形成が、人工光の不適切あるいは配慮に欠けた使用や運用、漏れ光によって阻害されている状況、又はそれによる悪影響」と定義。想定されている光害の影響範囲は、昆虫も含めた動物や植物、生態系、農作物や家畜など多岐にわたる。人への影響も、よく知られた天体観測だけではなく屋外照明の光が住居内に差し込むことによる安眠の妨げやプライバシーの侵害、不適切な街路灯などの選定により歩行者が不快なまぶしさを感じるといった内容も含まれる。都市部では、深夜まで営業する商業施設の明るい看板が住宅と近接している事例も少なくない。光害の問題は予想以上に深刻だ。自動車、船舶などの運行における標識や危険物察知などの視認性も、光害が及ぼす影響として想定されている。
山口大学の山本晴彦教授が取り組むのは、農作物への影響の問題である。「私が光害の問題に関わるようになったのは、2003年頃からです。ある日、ちょうどイネが穂をつける時期に水田の近くを歩いていたときです。田んぼの特定の部分だけ出穂(しゅっすい:穂が出ること)が遅れているのがはっきりと見て取れました。それも街路灯を中心に楕円状で、『光害だな』とすぐに分かりました」。水田の横には街路灯があり、その光が道路だけでなく背後のイネも照らしていたのである。そして、「街路灯の支柱の影ができる部分は順調に穂をつけていた。しかし、ポールの影にならない部分は明らかに開花が遅れていたのです」と振り返る。
植物の生長に光が必要なことはだれもが知っているが、光が当たることで生育に支障が出るというのはどのような理由なのだろうか。「イネは、夏から秋にかけて日が短くなる時期に穂を形成し出穂します。ここで出た穂が秋が深まるにつれて実り、収穫につながるのです。ですから、この時期に日が暮れても明るいという人間が夜の安全のために造った環境では、植物の開花や出穂が遅れ、また十分に生長することができずに収穫の時期を迎えてしまいます。当然収量は落ちますし品質も低下してしまうのです」。明るいときは明るく、そして暗くなるときにきちんと暗くならないことで植物に影響が出る。イネに限らずダイズなどでも同様のことが起こるという。
近年では、都市近郊では農地を宅地に転用させる(いわゆる「農転」)ことも増え、残った農地と住宅が近接する環境が増えている。またそうした空間では夜間であっても人が農道を行き来し、安全性の問題も指摘される。「車の脱輪や用水路への転落だけでなく、事件が発生した例もあります。農作物の生育と生活環境の安全性は、どちらも地域として重要で両立させなければならない課題なのです。夜間の照明が農作物にとってよくないことは、農家の人はみな知っています。しかし一般の方は暗い夜道は改善すべきと考える。この問題を解決できないか。山本さんは研究の動機をそう話す。
◎宅地化と、光害による農業生産への影響のアンビバレント
農林水産省の出身で、フィールドでの経験が長い山本さんは、田んぼを歩いていればわずかな異常に気づくという。また、農産物を育てるだけではなく、流通、消費まで幅広く見渡して植物工場の研究や実践も手がけてきた。植物工場の活用については、光と植物、気流や温度など植物の生育環境や、農産物の流通、スーパーマーケットでの売り方や価格まで、農業の「入り口から出口」を見つめる目を培ってきた。その視点は、農作物だけではなく、社会の変化や人の移動など、農業を取り囲むさまざまな角度から対象物を見つめる。
「国土が狭い日本において、宅地と農地が近接するという状況は、特定の地域にかかわらず多くの町で起こりえることです。でも『農産物にとって光が悪い』、『いや暗いと危ないではないか、防犯上も問題だ』とそれぞれの立場を主張したところで、解決の方向性は見えてきません」。そんな状況の中で山本さんが考えたのは、人には光として認知され、植物の生育に影響を及ぼしにくい照明の開発である。
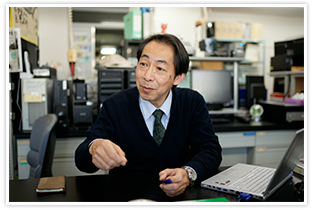 まず、光の色を制御すること。植物は光受容体によって自分がおかれた光環境を感じ取り、生きるために役立てている。植物の光受容体であるフィトクロムが反応するのは波長560~700nmの赤や橙、黄色などの光だ。これまで街灯に使用されてきた蛍光灯や水銀灯、ナトリウムなど生活用の照明のほとんどはこの波長を含んでいる。この光が生育に悪影響を及ぼすのであれば、もっと波長の短い、青や緑の光なら人にとっては光として感知され、イネの出穂が遅れる日数も短くなると考えた。「でもね、問題があるんです」。どういうことだろう? 「想像してみて下さい。夜道が青い光で照らされていたらどう思います?」と山本さんが笑いながら問いかける。「こわいでしょう? いくら明るくても、青い光は不気味なんです。夜、こんなところ歩きたくないでしょう?」。
まず、光の色を制御すること。植物は光受容体によって自分がおかれた光環境を感じ取り、生きるために役立てている。植物の光受容体であるフィトクロムが反応するのは波長560~700nmの赤や橙、黄色などの光だ。これまで街灯に使用されてきた蛍光灯や水銀灯、ナトリウムなど生活用の照明のほとんどはこの波長を含んでいる。この光が生育に悪影響を及ぼすのであれば、もっと波長の短い、青や緑の光なら人にとっては光として感知され、イネの出穂が遅れる日数も短くなると考えた。「でもね、問題があるんです」。どういうことだろう? 「想像してみて下さい。夜道が青い光で照らされていたらどう思います?」と山本さんが笑いながら問いかける。「こわいでしょう? いくら明るくても、青い光は不気味なんです。夜、こんなところ歩きたくないでしょう?」。
そんな条件の中で発案したのが、青や緑、黄緑までの光をミックスして「演色性」を高めることだ。不気味さを軽減して自然の光に近い色を作る。さらに、植物が光を受ける時間を少しでも短くしようと考えた。点灯時間を短くするということではなく、人の眼には点滅がわからないほどのきわめて短い時間で照明を点滅するパルス発光を取り入れて、植物には長日とならないように工夫した。明るさにも気を配る。一般に、街灯の明かりは最低でも3ルクスとされる。5ルクスで10m離れて人の顔が認知できるくらいの明るさだ。10ルクスならもっと見えやすくなるが、明るくなれば光害の影響が出やすくなる。5~10ルクス程度で、植物の出穂の遅れ日数の範囲を4日までと決め、2~3日までの遅れの範囲で、波長やパルスを制御したLED光源を開発した。「植物と人間、環境と快適性。いろいろな要素が相反する条件下では、それぞれが許容できる範囲から最終的な『落としどころ』を探し当てていくしかありません。その見極めに、経験や技術、実際に使う現場での知見が必要なのです」と、開発に留まらない社会実装に必要な意識を語る。
◎研究を社会に実装するには? 大学発ベンチャーの役割
さて、こうして開発した照明を実際に設置するためには、まだ越えなければならない壁がある。「大学の技術開発はびっくりするほどお金を使うでしょう? だからできあがったものはものすごく高い。これではお客さんは買いません」と、山本さんは現実的な製品の「出口」について語る。「発明」から「製品」へ。いいものを作って世に出すには、もう一工夫が必要だ。これら街灯などの照明器具の顧客は、道路管理者や地域の自治体などで、当然予算は限られる。また地域に見合った製品の仕様もさまざまだ。光源の開発を行い、製造はメーカー仕様にしたがって製造する。地域の事情をくみ取り、現実的なコストで、長持ちして管理も簡便であるなど、実用化し普及させるためには、「照明」の開発以外にさまざまな条件を整える必要がある。しかし、これを大学の研究として行うことはできない。
そこで必要なのが、生産技術の観点を取り入れてコンサルティングもできる、研究と製造工場を橋渡しする組織である。買う側と研究成果の間を取り持ち、どこを落としどころにするかといったことをベンチャー企業に担ってもらうというスキームを整える必要があった。
山本さんは、(株)アグリライト研究所という大学発ベンチャー 企業を立ち上げに参加し、研究の成果を活かすと同時に、応用展開を行うために必要な知見を積み重ねた。同時に、光害の現状や農作物への影響など現場のコンサルティングを行ったり、山本さんのもう一つの専門である、植物工場の活用や運営についての助言を行ったりすることを主な業務とする。そしてアグリライトのもう一つの大きな役割として、実際に設置し使用した状況をフィードバックしさらに研究や開発に活かす、PDCAサイクルを担うことである。
山本さんは、社長とはならず研究顧問として助言を行っている。大学の研究を社会に実装するために必要なし くみではあるが、ベンチャーを立ち上げ事業を継続していくのは、研究とは違った労力を要することも忘れてはならない。登記や事業計画、出資者との交渉、顧客管理など、研究とは異なる業務は山ほどある。アグリライトは順調に生長を続けているが、こうした経験からも大学ベンチャーのありかたや支援の仕方の問題も見えてきたという。大学ベンチャーが効果的に機能する仕組み作りについてもまだまだ課題が大きいということも言い添えた。
くみではあるが、ベンチャーを立ち上げ事業を継続していくのは、研究とは違った労力を要することも忘れてはならない。登記や事業計画、出資者との交渉、顧客管理など、研究とは異なる業務は山ほどある。アグリライトは順調に生長を続けているが、こうした経験からも大学ベンチャーのありかたや支援の仕方の問題も見えてきたという。大学ベンチャーが効果的に機能する仕組み作りについてもまだまだ課題が大きいということも言い添えた。






