本記事は、平成26年4月施行 の 「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例」
が施行される前の取材時の状況に基づいて作成されております。
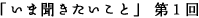
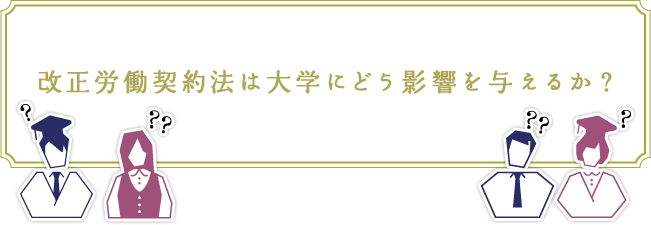
大学の研究職は、一般に人材が流動的であり、むしろ保証がないのが当たり前だと考えられている職種のひとつだと言われます。しかし労働環境や社会の変化により、最近では大学職員が裁判で「雇止め」の無効を争うケースも出てきました。次年度が始まる2013年4月1日は改正労働契約法の施行日にあたり、その日にスタートする多くの有期雇用契約がみな対象となります。大学や研究機関が人材を採用する際、どのような点に注意したらいいのか?──いくつかのケースに沿って見ていきましょう。
期限付き研究プロジェクトで雇用した特任研究員や研究支援員は、プロジェクト終了後も大学が無期雇用しなければなりませんか?


大学の研究室などでは、雇用の面でもやはりかなりの部分が、これまで人間関係で成立してきたと思われます。まず押さえておくべきなのは、改正労働契約法で定める「同一の使用者」とは、研究室単位ではなく労働契約締結の法律上の主体、すなわち大学や研究所といった法人単位であるということです。ある研究室で3年のプロジェクトに関わった後、大学内の別の研究室に誘われてまた3年間働くといったケースは比較的多いかと思いますが、雇用契約したのが同一の法人であれば、1回更新が入って5年を超えるので無期転換権が発生します。
研究室単位で見れば、たとえば科研費などの研究期間が終了したのでお金がないといった場合でも、母体である法人にリストラしなければならない客観的な事情があるのか、またその人が従事できる他の仕事がまったくないのか、またそれをやってみたのかといったことが一つ一つ問題になってきます。単に研究室にお金がないというだけでは解雇できないでしょう。
事務系職員などの有期雇用期間が5年を超え、本人の申込みがあったら、「正規雇用」に転換しなければならないのでしょうか?


本人の申込みがあった時点で無期雇用への転換が成立します(Q3を参照)。無期転換後の労働条件などについては「別段の定め」がない限り、期間以外の労働条件については、転換前と同一になります(Q2を参照)。しかし条文は期間についてのみ定めたものであり、その労働条件が最初から無期で雇用したいわゆる正社員の人たちと同一なのか、また既存の就業規則が適用されるのかといった具体的な内容にまで踏み込んでいくと、明らかになってくるのはこれからのことになると思われます。
いま予測できることとしては、就業規則に無期雇用者の労働条件などを加えるなどして対応しておかないと、無期転換後の契約内容がわからないという問題が起こってくるだろうことが挙げられます。また無期労働契約者のために、別立てで就業規則を作る場合には、正規雇用者との差がどのくらいまで認められるのか、今後の状況を見ながら見極めていく必要があるでしょう。
しかしながら有期労働契約を試用期間として捉え、労使双方にとって有効に活用していく道もあります。たとえば1年間有期雇用してみて適性を判断し、正式採用する、あるいは更新しないといった対処をしていくことも考えられるわけです。
2年契約を1回更新した有期雇用の研究者が、もし契約の途中で2年間の育児休業を取得したら、無期雇用しなければなりませんか?


通算契約期間は労働契約の存続期間で計算しますが、育児休業中も、給料が払われるかどうかには関わりなく、その期間も含めて算出します。このケースでは、たとえば2013年4月1日から契約開始したら、2回目の契約期間は2019年3月31日に満了となり、5年を超えてしまいます。したがって雇用者が、育児休業中を含む2回目の契約期間中に申込みをすれば、無期契約に転換することになります。
なお研究という観点から考えると、特任研究員やポスドク、特定の技能を持った技術系職員などの人々をたくさん「雇用」してしまうと、まさしく改正労働契約法の対象となってしまい、新しい研究ができないといった弊害も十分予想されます。そこで技術研究系の人材は、雇用ではなく「業務委託」に切り替えるという対応が考えられると私は思います。研究室やプロジェクト単位で業務を委託しているという意味で、実際の内容としても業務委託という形態に合致すると思われますし、研究に関連して守秘義務が必要ならば、契約内容に盛り込むこともできます。研究を法人組織として行っていくために、雇う側として活用できるところではないでしょうか。なお研究・技術系の職員とは異なり、事務など専門性のない職員の場合は業務委託にはあたらず、法の網をかいくぐる「偽装請負」ということになってしまいますから、注意が必要です。
次ページでは、雇用される立場から、改正労働契約法を見ていきましょう。






