昨年、「ゾウの鼻はだてに長いのではなく、その能力も非常に優れている」という研究を共同発表した新村芳人 特任准教授。東京大学大学院農学生命科学研究科で、ERATO 東原化学感覚シグナルプロジェクトの一角を担う。「そもそもは素粒子を研究したかった」という物理出身。統計数理的にゲノムを比較することによって進化の経緯をたどる「分子進化」と呼ばれる分野が専門である。そしてこの方法によって、哺乳類の嗅覚受容体遺伝子の多様性を俯瞰的に理解する重要な手がかりが得られたことが、この研究の大きな特徴なのだそうだ。さらに解析を進めるとどんなことがわかるのか?──今、新たなテーマにも挑みつつあるという、新村芳人特任准教授にお話をうかがった。
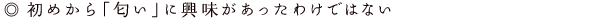
 20世紀の後半から、分子レベルで生命を理解しようとする分子生物学が発達し、1995年に生物全体のゲノム情報が初めて明らかにされました。私はちょうど大学院生で、コンピュータで生物をまるごと解析できる、これはすごいと興奮したことを覚えています。バクテリアなど、さまざまなゲノムを比べることによって進化の道筋が見えてくる。直接実験できなくても、その生物の性質を調べることができる。そしてゲノムがA,T,G,C 4種類の塩基で構成されているということはどんな生物にも共通しているので、あらゆる生物を同じ方法で研究することができます。このようなバイオインフォマティクスという分野があることを知ったのも、生物へ転じた一因でした。
20世紀の後半から、分子レベルで生命を理解しようとする分子生物学が発達し、1995年に生物全体のゲノム情報が初めて明らかにされました。私はちょうど大学院生で、コンピュータで生物をまるごと解析できる、これはすごいと興奮したことを覚えています。バクテリアなど、さまざまなゲノムを比べることによって進化の道筋が見えてくる。直接実験できなくても、その生物の性質を調べることができる。そしてゲノムがA,T,G,C 4種類の塩基で構成されているということはどんな生物にも共通しているので、あらゆる生物を同じ方法で研究することができます。このようなバイオインフォマティクスという分野があることを知ったのも、生物へ転じた一因でした。
物理学には、宇宙の森羅万象をひとつの方程式で理解したいという根本的な欲求があります。一方生物を理解しようと思ったときに、生物の統一理論は何だろうか?……と考えると、それは進化なんですね。「あらゆる生命現象は進化の光に照らしてみないと意味がない」と言ったのはウクライナ生まれの進化生物学者、ドブジャンスキー(Theodosius Grygorovych Dobzhansky, 1900 - 1975)ですが、私もゲノムで進化を研究したいと思ってアメリカへ留学しました。そして分子進化という学問を創始したひとりである根井正利先生に、匂いを感知する「嗅覚受容体」というテーマをいただいたのが、2002年頃のことでした。
嗅覚はまず、環境の中にあって匂いの元となる「匂い分子」が、鼻腔の嗅上皮にある嗅覚受容体に結合することによって起こります。環境には多様な匂い分子が存在するため、嗅覚受容体を受け持つ遺伝子は多数あり、嗅覚受容体は最大の「遺伝子ファミリー」と言われています。マウスのゲノムには約1,100個、ヒトでは約400個もの嗅覚受容体の遺伝子があり、互いに遺伝子を構成する塩基配列が似通っています。これらの遺伝子を祖先へとさかのぼっていくと、やがて1つの「祖先遺伝子」に行き着きます。このように祖先遺伝子から、遺伝子重複と突然変異を繰り返し、進化してきた遺伝子のグループを「遺伝子ファミリー」といいます。嗅覚受容体遺伝子の進化を研究することによって、嗅覚そのものに対する理解だけでなく、遺伝子ファミリーの進化についての一般的な理解が得られるのではないか? また環境とも関わることから、その生物の生育環境がどのように変わってきたかというマクロな進化への示唆も得られるのではないか?──と考えています。
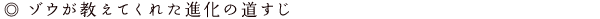
 われわれはまず、哺乳類のなかの真獣類にあたる13種の生物に注目しました。中でもゾウは、13種の中で進化的に最初に分岐したことから他の12の真獣類と並び立つ関係にあり、しかもゾウの嗅覚受容体の遺伝子の数が一番が多いことがわかりました。このような系統的な関係をうまく使うことによって、祖先がどういう遺伝子を持っていたのか、13種が持つそれぞれの遺伝子が、どの祖先遺伝子に由来するのかを効率よく推定していったわけです。これによって真獣類13種の共通祖先の嗅覚受容体遺伝子が781個あったことがわかりました。
われわれはまず、哺乳類のなかの真獣類にあたる13種の生物に注目しました。中でもゾウは、13種の中で進化的に最初に分岐したことから他の12の真獣類と並び立つ関係にあり、しかもゾウの嗅覚受容体の遺伝子の数が一番が多いことがわかりました。このような系統的な関係をうまく使うことによって、祖先がどういう遺伝子を持っていたのか、13種が持つそれぞれの遺伝子が、どの祖先遺伝子に由来するのかを効率よく推定していったわけです。これによって真獣類13種の共通祖先の嗅覚受容体遺伝子が781個あったことがわかりました。
続いて、この781個を比較して遺伝子の個性を見ていきます。すると、もともと1個だった遺伝子がゾウだけ84個にも増えているのがある。これはゾウだけに特有なので、ゾウにとって非常に重要な機能をもつのではないかと推測できます。一方、13種の生物がそれぞれ1つずつ持っている遺伝子が、3種類だけあることもわかりました。そしてこれらの遺伝子は、ふつう発現する嗅上皮ではなく、鼻以外の臓器で発現し、いろいろなところで働いていました。嗅覚受容体は外界の匂い分子と相互作用するため、匂い以外のいろんな用途に使い回すことができると言えます。すると推測されることは、匂い以外の機能を持っているということ、そして何らかの必要があってなくならなかったこと、そして遺伝子の数が増えても不都合があったということです。だから、ずっとそのまま保存されているわけです。
嗅覚受容体遺伝子をより広く見渡すと、GPCR(G protein-coupled receptor)というもっと大きな遺伝子グループの一部分を構成しています。GPCRは細胞膜を7回貫通する構造を持ち、ドーパミンなど脳内の神経伝達物質を受け取る受容体、色覚を司るオプシンなどもこれに含まれます。しかし、その中で嗅覚受容体が最も繁栄したのは、環境の中からどんな匂い分子が来るか予測できない時に、どう備えたらよいかという問題があったからです。これによく似ているシステムといえば……免疫系ですね。しかし免疫系が遺伝子組み換えで多様性を出しているのに対して、嗅覚系は遺伝子の数を増やすというシンプルな戦略を採っています。数が増えれば、より多くの匂いを嗅ぎ分けられるようになる。ゾウが多くの嗅覚受容体を持っているということは、それだけ匂いの識別能力が高いと考えられます。
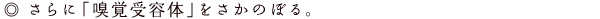
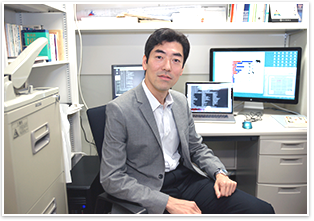 ところでイヌの鼻が利くことは有名ですが、遺伝子の数は約800個と意外と少ない。イヌは肉食なので、餌となる匂いに特化して感度が高いと考えることができ、例えばヒトの体臭の元である脂肪酸については、ヒトの1億倍もの嗅覚を持つとも言われます。機能を維持するには遺伝的なコストがかかりますから、一つの感覚がよくなると、より重要でない別の感覚が失われるということなんですね。霊長類の場合はやはり視覚優位なので、嗅覚受容体遺伝子は比較的少ないと言えます。ところが霊長類の中でもとりわけヒトは嗅覚が鈍いと考えられがちですが、遺伝子数を見ると実際にはオランウータンよりも多いことがわかりました。では海に生息するイルカはどうなのか、コウモリはどうか……というようにいろんな動物を調べてみて、彼らが生息する環境とどう関係しているかを、今、調べているところです。
ところでイヌの鼻が利くことは有名ですが、遺伝子の数は約800個と意外と少ない。イヌは肉食なので、餌となる匂いに特化して感度が高いと考えることができ、例えばヒトの体臭の元である脂肪酸については、ヒトの1億倍もの嗅覚を持つとも言われます。機能を維持するには遺伝的なコストがかかりますから、一つの感覚がよくなると、より重要でない別の感覚が失われるということなんですね。霊長類の場合はやはり視覚優位なので、嗅覚受容体遺伝子は比較的少ないと言えます。ところが霊長類の中でもとりわけヒトは嗅覚が鈍いと考えられがちですが、遺伝子数を見ると実際にはオランウータンよりも多いことがわかりました。では海に生息するイルカはどうなのか、コウモリはどうか……というようにいろんな動物を調べてみて、彼らが生息する環境とどう関係しているかを、今、調べているところです。
また嗅覚受容体と他のGPCRは、進化的にどういう関係にあるかというのも興味深いテーマです。たとえば哺乳類の嗅覚受容体の進化をさかのぼっていくと、脊椎動物が含まれる「脊索動物」というグループの中に「ナメクジウオ」という生物がいます。このナメクジウオと、約7億年前に生きていた脊索動物の祖先も、やはり嗅覚受容体遺伝子を持っていたことがわかっています。ところがもっとさかのぼるとこの遺伝子が存在しない。一方昆虫では、GPCRとは別の遺伝子ファミリーを嗅覚受容体として使っており、ハエの嗅覚受容体は60個ぐらいしかありません。つまり嗅覚という機能やシステムは似ているけれども、使っている遺伝子が違うのです。すると嗅覚受容体遺伝子は、進化の過程で何回も独立に作られてきたことがわかってきます。このようにして、いろんな生物のゲノムを解析し、遺伝子ファミリーごとの違いを比較する研究にも取り組んでいます。






