国立大学はいま、人文社会科学系の学部・大学院の廃止や他分野への転換を含む大規模な組織改編の時期を迎えている。……そのような中、「基本的には積極的に人文学に意義を出していくしかない」というのは、東欧・ロシアにおけるシオニズム(19世紀末に始まった、ユダヤ人の民族的拠点をパレスチナに作ろうとする思想・運動)を研究する埼玉大学鶴見太郎准教授。数カ国語を駆使して文献を読み込み、「パレスチナ問題になんとか突破口を見つけたい」という強い動機と交叉させる。政治的な偏りに組みしない、社会学的あるいはより広く人文学的なアプローチを持つ日本の文系研究者として「国際的な研究コミュニティをつなぐ役割も果たしていきたい」という鶴見准教授に、埼玉大学の研究室にてお話をうかがった。

 大学生の頃もイスラム圏の紛争が活発で、なぜああいう紛争が起きているのか、どうしてああいうことになったのかという関心が最初にありました。パレスチナ/イスラエルという地域については、その発端が、ユダヤ人が自分達の民族的な拠点をつくるという「シオニズム思想」とその運動にあることは明らかであり、かの地に元々住んでいたアラブ系の人たちとの間で起こった紛争が、今日まで続いているわけですね。この紛争にはおよそ100年の歴史がある。そもそもなぜシオニズムが始まったのか?──中でもその母体となったロシア帝国・東欧地域に着目して、シオニズムを紛争の背景として理解する研究を行っています。
大学生の頃もイスラム圏の紛争が活発で、なぜああいう紛争が起きているのか、どうしてああいうことになったのかという関心が最初にありました。パレスチナ/イスラエルという地域については、その発端が、ユダヤ人が自分達の民族的な拠点をつくるという「シオニズム思想」とその運動にあることは明らかであり、かの地に元々住んでいたアラブ系の人たちとの間で起こった紛争が、今日まで続いているわけですね。この紛争にはおよそ100年の歴史がある。そもそもなぜシオニズムが始まったのか?──中でもその母体となったロシア帝国・東欧地域に着目して、シオニズムを紛争の背景として理解する研究を行っています。
20世紀初頭、ドイツの52万人に対して、ロシア帝国には519万人ものユダヤ人が住んでいました。中世にポーランドの貴族がユダヤ人を重用したため、そのユダヤ人の多くがポーランドの大部分がロシア帝国に編入されたのと同時にロシアの臣民になったことも大きな要因のひとつです。一方ロシア帝国の中にはポーランド人、ドイツ人、ギリシア人など他にもさまざまな民族がいました。しかし彼らはユダヤ人ほどは迫害されていなかった。なぜユダヤ人だけが差別されるのか? ユダヤ人は自ら分析し、その原因が本国という拠点を持っていない点にあると考えるようになっていきます。一方で、ロシア帝国に長く暮らしてきたユダヤ人たちは、その国に同化し、中堅以上の世代を中心にロシア化の傾向を強く持ってもいました。つまりシオニズムの核心とは、全員が移住するとか、差別から逃げるとかいったことではなくて、自尊心を持つことで、他の民族に同化しないように、また、政府や他の民族からそれなりに尊重される存在になろうという考えにあるんですね。
1917年にはロシア革命が起こりました。ソ連時代、ユダヤ人政策は大きく転換して、結果的にシオニズムにとっては好ましくない方向へ進んでいきました。しかも同時期に起こった第一次世界大戦(1914-1918)が、ユダヤ人により大きなインパクトをもたらします。ロシア帝国も戦場となり、その混乱の中で敵と味方の板挟みに合い、反ユダヤ主義のような偏見も加わっていろいろな理由を押しつけられて迫害が起こる。迫害といってもこれまでとは桁違いの殺戮が行われ、日常的に暴力というものを目の当たりにするんですね。第二次世界大戦では、周知のようにこの傾向がさらに苛烈になって、歴史はホロコーストへの道を歩んでいくわけです。

 シオニズムという思想・運動を生んだ背景を考えるためには、社会学的な思考が重要だと考えています。ユダヤ人がマイノリティだったという条件に注目すれば社会学的テーマであることは明白ですが、それだけではなく、社会学は、明確な政治的主張を背後で支え、その活動に文脈を与えるような「世界観」に着目する学問だからです。彼ら自身は運動をどのような意味連関として理解していたのか、たとえばそれが政治という次元でどの点だったら妥協でき、あるいはできないのか……本人たちの具体的な主張とは別に、言葉の深さや背景からその意味を理解していく視点が非常に重要です。
シオニズムという思想・運動を生んだ背景を考えるためには、社会学的な思考が重要だと考えています。ユダヤ人がマイノリティだったという条件に注目すれば社会学的テーマであることは明白ですが、それだけではなく、社会学は、明確な政治的主張を背後で支え、その活動に文脈を与えるような「世界観」に着目する学問だからです。彼ら自身は運動をどのような意味連関として理解していたのか、たとえばそれが政治という次元でどの点だったら妥協でき、あるいはできないのか……本人たちの具体的な主張とは別に、言葉の深さや背景からその意味を理解していく視点が非常に重要です。
私の場合は、大量に出版されていた印刷物、本、パンフレットなどをとりあえず探る中で、主にイスラエルの図書館に集められている社会運動家の定期刊行物に着目していきました。まさに「新聞を読んで現代を知る」というのと同じように、定期刊行物を読むことで社会運動家というある種のエリートの考え方を通じて一般の人々の生活も推し量ることができ、当時の情況がいろいろとつながっていったのです。当事者がどんな意味を見出していたのか?……というこの視点は、特に外国研究で不足しがちなものだと考えています。実際、どこの国の社会学でも、基本的に自国の社会について深く掘り下げる研究が大半で、他方、外国研究では現代にしても歴史にしても政治学的・経済学的な観点か思想・文学が中心です。本来ならば外国に関しても同様に重要なはずのこのような社会学的な視点は不足していると言えるでしょう。
結局、外国語を学ぶためには、その言葉や文法を学ぶしかないのと同じように、あるコミュニティを知ろう、作ろうという場合には、そこにいる人々の間に流通している想像力や、人々をつないでいる論理を理解することに尽きると思います。語学はただの入口であって、研究対象とじっくり付き合うための訓練が、当然必要になります。そして人々が行うコミュニケーションは絶えざる動きであり、ずっとつながっているものですから、何かある時点を切り取って一般化することはできない。もし地球上にたった1つしかコミュニティがないならば、一般化も簡単かもしれません。けれどもコミュニティは絶えず見出され、作り出され、変化しているので、やはり常にそれに対応する必要があるのです。
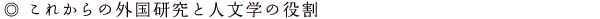
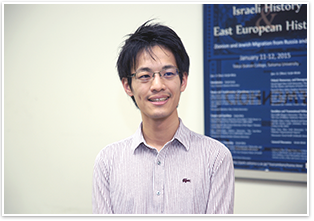 人文学の重要な役割のひとつは、やはり価値観や世界観を含めた、「意味」への着目だと考えています。とにかく意味を探る、理解するというところを除いては説明できない事象がたくさんある。結局それは人間にしかできないことであり、まさに人間が人間であるがゆえに残る領域である、としか言いようがありません。しかも意味というのは1人で決めることが出来ない性質を持っています。たとえば「私はこの意味でこの言葉を言った」といっても通じない。その宣言自体が、独りよがりな印象を与えたり不信感を抱かせるといった形で、また別の意味を生み出していくわけですね。そうした性質を持つ人間社会のなかの意味をとらえるには、意味の連なりや体系を研究する以外ありません。
人文学の重要な役割のひとつは、やはり価値観や世界観を含めた、「意味」への着目だと考えています。とにかく意味を探る、理解するというところを除いては説明できない事象がたくさんある。結局それは人間にしかできないことであり、まさに人間が人間であるがゆえに残る領域である、としか言いようがありません。しかも意味というのは1人で決めることが出来ない性質を持っています。たとえば「私はこの意味でこの言葉を言った」といっても通じない。その宣言自体が、独りよがりな印象を与えたり不信感を抱かせるといった形で、また別の意味を生み出していくわけですね。そうした性質を持つ人間社会のなかの意味をとらえるには、意味の連なりや体系を研究する以外ありません。
もちろん人文学にもいろいろあって、たとえば社会科学寄りの分野の場合はむしろ自然科学的な研究の設計をする傾向が強いでしょう。しかし社会なり、人と人との間を見ようとするときに、事象を安易に切り取ってそれだけを対象とするようなアプローチは無効であると言わざるを得ません。そのことが人文学のわかりにくさ、曖昧さにつながっていることは事実でしょう。人文学が役に立たない、要するにお金儲けにつながらないという最近の議論もそのことが関係しているかもしれません。しかも、人文学者は潔癖を貫き、これまで決して「儲かる」部分を強調して来なかった。というのも、そのように"手垢の付かない"立場であることが、実は人文学的には決定的に重要な立場だからです。国際競争の中で大学が日本企業を後押しするような役割を担うならば、特に理系は学問を国家の線に沿って切る方向へと向かうのではないでしょうか。これは科学の発展にとってマイナスです。一方人文学の場合は、歴史認識問題に代表されるように、もともと国境に影響されやすい側面を持っています。しかしだからこそ、それをあえて乗り越えて普遍的真理や共通点を見出すことが重要で、またそのことによって国境を全否定するのではなく、ありのままに見ることができるようになるのではないでしょうか。その際、国単位での競争はやはり有害でしかありません。
私の場合は、ロシア、イスラエル、パレスチナをキーワードとする分野を、日本ではなく紛争地域に新しい風を吹き込むために、私自身が「つなぐ」役割を果たしたいと考えています。そのひとつの試みとして、今年はロシアを含む東欧史の文脈にイスラエルを位置づけるシンポジウムを開催しました。今回の参加者は歴史の専門家がほとんどでしたが、体系的に議論を立ち上げ、いずれは紛争を扱う研究者のコミュニティもつないでいこうという長期計画です。非常に政治化した地域を対象としているため、実際シオニズム研究者のほとんどはユダヤ人であり、パレスチナ人の研究者とは交流が少ないことは確かですし、広い意味での利害関係や対立が、どうしても存在します。人文学は、まさに研究者が人間であることの影響を強く受けるという一例ですが、そこにこそ、イスラエル研究を日本で行う意義があるのではないでしょうか。経済的な利益は生みませんが、世界に大きな価値をもたらす可能性があります。






