2012年度のつながるコンテンツは、テーマも新たに「明日へとつなぐ鍵」としてスタートする。その第一回目として今回は、団地、鉄道、天皇制といった複数のユニークな視点から政治思想史を捉える、明治学院大学国際学部の原武史教授にお話をうかがった。2007年の『滝山コミューン一九七四』では、東京郊外にあるマンモス団地の小学校で、実際に起こった自身の体験を遡行。鉄道に関する講演で、出張先のベトナムからちょうど帰国したばかりという原教授を、横浜市・戸塚の研究室に訪ねた。
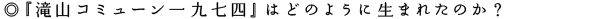
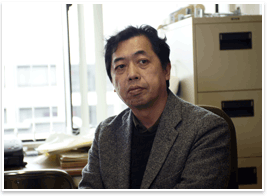 滝山団地は西武沿線に建てられた公団で、幼少時、僕はその団地に住み、その一角にあった小学校に通っていました。『滝山コミューン一九七四』は、その小学校で集団主義的な教育が行われた、僕が4〜6年生までの体験を書いたものです。要するにマイ・ヒストリーなんですが、しかし書くことでずいぶん目の前が拡がって、結果的に思いも寄らなかった分野に足を踏み出したんじゃないかと思っています。誰しも幼少期の体験が、なんらかその後の人生を規定しているという面があると思いますが、滝山を体験していなければ、僕はたぶん政治思想なんかに関心を持たなかった(笑)。なぜ人間というのはこんなにも簡単に洗脳されるのか、不思議だなあと思いました。その時の僕は、なぜこのような体制が生まれるのか、よくわからなかった。
滝山団地は西武沿線に建てられた公団で、幼少時、僕はその団地に住み、その一角にあった小学校に通っていました。『滝山コミューン一九七四』は、その小学校で集団主義的な教育が行われた、僕が4〜6年生までの体験を書いたものです。要するにマイ・ヒストリーなんですが、しかし書くことでずいぶん目の前が拡がって、結果的に思いも寄らなかった分野に足を踏み出したんじゃないかと思っています。誰しも幼少期の体験が、なんらかその後の人生を規定しているという面があると思いますが、滝山を体験していなければ、僕はたぶん政治思想なんかに関心を持たなかった(笑)。なぜ人間というのはこんなにも簡単に洗脳されるのか、不思議だなあと思いました。その時の僕は、なぜこのような体制が生まれるのか、よくわからなかった。
『滝山』を書いてから、これをもう少し学術的に掘り下げたいという思いが生じて、それが今年2つの本として出版されます。ひとつは西武という私鉄の沿線の戦後思想史を辿る『レッドアローとスターハウス(近刊)』。もう一つは団地という政治空間に焦点を当てた『団地の空間政治学(近刊)』で、西武沿線のひばりが丘団地や滝山団地に限らず、東京なら高島平団地(板橋区)・多摩平団地(日野市)・常盤平団地(松戸市)・高根台団地(船橋市)・多摩ニュータウン(多摩市など)、大阪なら香里団地(枚方市)・千里ニュータウン(豊中市・吹田市)といった具体的な団地を採り上げ、50〜70年代の大都市近郊のマンモス団地が果たした政治思想史的役割を検証するものです。
ところで歴史を書くときに、事実そのものがあるという前提は、意味をなさないと思っています。それは学術的な著作でも同様であって、客観的な歴史というものはあり得ない。資料を取捨選択して書くという作業自体は同じであり、そこにある種の主観が入り込んでいるんですね。この意味ではノンフィクションだって、みんなフィクションであって、本来はそういう共通の土俵のなかで論争というものが起こるべきだと思う。ただ僕は、書く時には断定しないよう心がけています。つまり、この資料によればそうだとしか言えないわけだから。また誰かを想定して書くという感覚もあまりなくて、まあ要するに自分がおもしろいと思うことを伝えるために書いていますね。

 滝山団地は、どこへ行くにも西武のバスや鉄道に乗らなければならないという、典型的な西武沿線の団地のひとつでした。日本の鉄道、特に都市近郊の私鉄の多くは、明治から昭和初期にかけて敷設されていくのですが、ただ単に都心と郊外を結んで往復するだけではなくて、その上に生活や文化を作っていくんですね。これを最初にやったのは阪急の小林一三で、しだいに関西私鉄全体に広がり、阪急が築いた宝塚や阪神が築いた甲子園は、戦後も残って発展していきます。首都圏では東急の五島慶太が1950年代に自ら多摩丘陵を歩いて、こつこつと地主を説得して土地を買収していき、これが後の多摩田園都市になる。土地をいったん白紙状態に戻して、山だったのがひな壇になり、そこに戸建てが建ち並ぶようになり、電車が開通して、駅名も地名も全部新しいものにしていく。
滝山団地は、どこへ行くにも西武のバスや鉄道に乗らなければならないという、典型的な西武沿線の団地のひとつでした。日本の鉄道、特に都市近郊の私鉄の多くは、明治から昭和初期にかけて敷設されていくのですが、ただ単に都心と郊外を結んで往復するだけではなくて、その上に生活や文化を作っていくんですね。これを最初にやったのは阪急の小林一三で、しだいに関西私鉄全体に広がり、阪急が築いた宝塚や阪神が築いた甲子園は、戦後も残って発展していきます。首都圏では東急の五島慶太が1950年代に自ら多摩丘陵を歩いて、こつこつと地主を説得して土地を買収していき、これが後の多摩田園都市になる。土地をいったん白紙状態に戻して、山だったのがひな壇になり、そこに戸建てが建ち並ぶようになり、電車が開通して、駅名も地名も全部新しいものにしていく。
東急の開発に比べると、西武の場合はかなり中途半端なんですね。堤康次郎は東京の西郊に3つの学園都市を作ろうとするのですが、大泉と小平は誘致した大学が結局移転して来ず失敗し、中央線の国立だけが成功する。ちなみに現在もある「大泉学園」「一橋学園」という駅名はその名残です。一方1950年代の後半から、農村地帯が広がっていた西武沿線に住宅公団が進出していきます。団地ができるにつれ、60〜70年代には西武もイメージアップして、沿線の人口が増えていく。ところで考えてみれば、鉄道は行政的な境界を乗り越え、「練馬区民」「清瀬市民」「所沢市民」といった意識よりももっと強い、「西武沿線住民」という意識を作ります。特に西武は阪神同様、野球チームがありますからなおさらです。こういった視点は、行政学的には見えにくいところですが、きちんと見ていかなければならないでしょう。
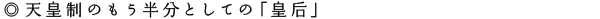
 ところで現在はまた違うテーマで、以前から関心のあった近代天皇制の、特に皇后に注目して取り組んでいるところです。つまり──今までの天皇制の研究で決定的に欠けているのは、天皇/男ではなく、皇后/女の側ではないか、と。そもそも明治維新で天皇が京都から東京へ移る時に、天皇制が大改造されます。京都御所にいた天皇は女たちに取り囲まれ、複雑な人間関係があって、皇后と呼ばれる存在もいませんでした。ところが東京ではそういう習慣を廃止し、天皇は髭を生やし、軍服を着るなど、いわば男性化されます。一方、不平等条約の条約改正を急いでいた明治政府は西欧諸国を意識して、皇室にも一夫一婦という近代的な家族を演じてもらわなければならなかった。そこで天皇と同時にそのパートナーとしての皇后も作られていくんです。
ところで現在はまた違うテーマで、以前から関心のあった近代天皇制の、特に皇后に注目して取り組んでいるところです。つまり──今までの天皇制の研究で決定的に欠けているのは、天皇/男ではなく、皇后/女の側ではないか、と。そもそも明治維新で天皇が京都から東京へ移る時に、天皇制が大改造されます。京都御所にいた天皇は女たちに取り囲まれ、複雑な人間関係があって、皇后と呼ばれる存在もいませんでした。ところが東京ではそういう習慣を廃止し、天皇は髭を生やし、軍服を着るなど、いわば男性化されます。一方、不平等条約の条約改正を急いでいた明治政府は西欧諸国を意識して、皇室にも一夫一婦という近代的な家族を演じてもらわなければならなかった。そこで天皇と同時にそのパートナーとしての皇后も作られていくんです。
しかし明治天皇の時代には、実態としてはまだハーレム的な世界が存続していたんですね。これが大正天皇の時代になると、実態としても一夫一婦制となり、しかも4人の男の子が生まれて、皇后の力はますます強大になっていきます。夫の大正天皇が体調を崩すと、貞明皇后(大正天皇の妃)は『日本書紀』に登場する仲哀天皇の妃に当たる神功皇后や、聖武天皇の妃に当たる光明皇后に自らを重ね合わせるようにして、神功皇后をまつる福岡県の香椎宮を参拝したり、ハンセン病患者を支援したりするようになります。なぜ貞明皇后はそのような力を発揮できたのか?──もちろんその理由は、大正天皇が病気になって引退させられたのが大きくて、もし病気にならなければ、むしろ明治国家が設定した枠に収まっていたのではないかと思いますね。戦前までは、宮中はもちろん学校教育でも万世一系の天皇はすべて実在の人物だと教えられていましたし、天皇の祖先とされるアマテラスの存在も大きかった。そんな中で天皇が原因不明の病気にかかり、加えて関東大震災も起こります。このような不慮の事態に直面した皇后は、アマテラスの神威というものを否応なしに感じるようになります。神をおそれなければならないという気持ちが、かえって皇后の巫女的な体質を強めさせたのではないか……と、僕は思っています。
ハンセン病患者のような、最も恵まれない人々に最も手厚い慈愛のまなざしを注がなければならないとする貞明皇后の考え方は、政治や軍事をつかさどる天皇に対してマージナルだったわけですが、今や戦後を生き残った皇室の中心に浮上しています。特に平成の天皇制は、皇后が持っているある種の宗教的な力で支えられているという部分が大きいと思う。そして震災も含めて、特に大正の後半と平成の後半の状況がかなりよく似ているんですね。大正の皇室を研究することは、現在われわれが置かれている状況を考えるための深い視点を与えるのではないかと考えています。






