人間を含めた生物の脳がどのように活動しているのか、今世紀に入って人類の知識は大きく飛躍した。しかしながら、このいわゆる「脳科学」という分野、具体的に何が解明されたのか、どことどこがつながっているのか、門外漢にはなかなか理解しにくいことも多いと言えるのではないだろうか。さて、2015年度researchmapの新テーマは「トビタつための星」。その第1回目のインタビューは、神経科学を専門とする奈良先端科学技術大学院大学 駒井章治 准教授にお話をうかがった。
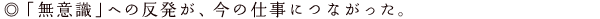
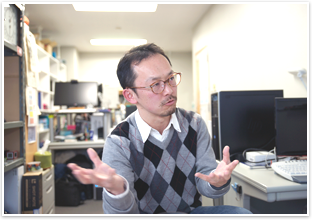 高校生の時、ずっと理系志望で勉強していたのですが、ある日ふと周囲を見回して「何か違うな」と思ったんです。そこで、自分のやりたいことができる文系の学科を探したら、心理学科だったんですね。ところが心理学科に入って実際に勉強が始まってみたら、どうも「無意識」というものがものすごく重要であるようなのだけれども、それが何なのか、どうも馴染めない(笑)。いつかこの「無意識」を駆逐しようと思って、生理心理学へ進みました。生理心理学は、指先の発汗を測ったり、脈や血圧といった生き物の生体反応をいろいろ測って、心の動きを読むといった研究活動を行う分野ですから、現在の仕事に比較的近いんですね。
高校生の時、ずっと理系志望で勉強していたのですが、ある日ふと周囲を見回して「何か違うな」と思ったんです。そこで、自分のやりたいことができる文系の学科を探したら、心理学科だったんですね。ところが心理学科に入って実際に勉強が始まってみたら、どうも「無意識」というものがものすごく重要であるようなのだけれども、それが何なのか、どうも馴染めない(笑)。いつかこの「無意識」を駆逐しようと思って、生理心理学へ進みました。生理心理学は、指先の発汗を測ったり、脈や血圧といった生き物の生体反応をいろいろ測って、心の動きを読むといった研究活動を行う分野ですから、現在の仕事に比較的近いんですね。
そもそも脳を考えるということ自体、神経科学だけでなく数理心理学、数理神経科学、神経哲学といわれる分野、あるいはロボットの研究者などが、これを知りたいというテーマに基づいて集まっている、融合的な分野なんです。一方「脳科学」というと、最近テレビ番組などでいろいろ採り上げられて……研究によれば、みなさんの行動は、実はこういうしくみで……といった解説がよくなされていますね。でも、もう一歩踏み込んで考えてみたら、そのような解説は結局何も説明していないのではないか? そういった理解の仕方は、やっぱりよくないんじゃないか、と思うんです。自分は心理学出身だからこそ、漠然としたことをきちっと理解し、解決したいなと思う。つまり、脳はどうやって動いているのだろうか?──脳の機能の最小単位を理解したいな、と。
一方、テクノロジーが非常に発達してきて、いろんな実験が可能になってきています。顕微鏡を使って脳の活動を細かく調べたり、脳を操作することもできるので、たとえば光を使って細胞1個1個を刺激したり、頭に傷をつけずに外から強い磁場をかけてある部位だけを刺激したり、といったこともできるようになってきました。ところが、脳をほんのちょっと刺激したとして、それによってちょっとだけ変化した行動を僕たちはどう評価すればいいのでしょうか? つまり、脳の状態に対応する「行動の解析」がまったく進んでいないのです。このような「ちょっとの違い」を人間が見て、客観的に評価することはほぼ不可能だと言えるでしょう。そこで、コンピュータを使って特徴量をとるという研究を進めています。
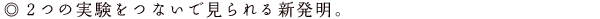
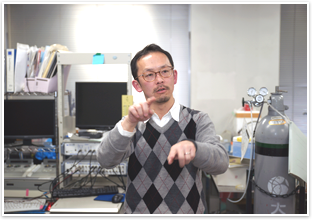 2003年から約2年間は、ドイツのマックス・プランク医科学研究所にある、2光子レーザー走査顕微鏡という装置を開発した研究室に留学しました。その少し前から活発だったのが記憶の実験で、動物の脳の中にある特定の分子を破壊し、その脳をスライスにして電気の活動を計測して、電気生理学的に細胞と細胞のつながり方をみる。もう一方で同じ動物を行動させて観察し、この分子は記憶のこの部分に関係していることをつきとめる。この2つのアプローチを組み合わせた論文が、数多く発表されていました。でもこれでは、脳の状態と行動という2つが、直接には結びついていません。「一緒にできないか?」と思っていた時に、ちょうどそれを可能にする新しい顕微鏡に出会ったのです。
2003年から約2年間は、ドイツのマックス・プランク医科学研究所にある、2光子レーザー走査顕微鏡という装置を開発した研究室に留学しました。その少し前から活発だったのが記憶の実験で、動物の脳の中にある特定の分子を破壊し、その脳をスライスにして電気の活動を計測して、電気生理学的に細胞と細胞のつながり方をみる。もう一方で同じ動物を行動させて観察し、この分子は記憶のこの部分に関係していることをつきとめる。この2つのアプローチを組み合わせた論文が、数多く発表されていました。でもこれでは、脳の状態と行動という2つが、直接には結びついていません。「一緒にできないか?」と思っていた時に、ちょうどそれを可能にする新しい顕微鏡に出会ったのです。
この2光子レーザー走査顕微鏡は、非常に短い時間感覚で光をポン、ポンと2度エネルギーが約半分の長波長の光を照射することで蛍光物質を「励起」させます。長波長の光を使うため、脳の奥まで光を当てることができ、且つ生体に与えるダメージを少なくすることができる画期的なツールでありイメージング分野が更に発展することになりました。僕はこれを使って、破壊された細胞を生きた動物の個体の中で観察し、さらにその細胞から電気的にその活動を記録できるようにしよう、という研究をしたのです。その後アメリカで、クラミドモナスという藻類からとれる、光を感受してチャネルを開く機能を持つ物質を使った「光遺伝学」という新しい手法を用いた研究が始まりました。この物質を神経細胞にいれておいて、ある波長の光を当てると、そのチャネルを発現している細胞だけを興奮させることができます。いわば光によって一定時間オンにしたりオフにしたりできるスイッチとして使うことができるんですね。
このようにして脳の状態が測れるようになってきたら、今や、本当に解明しなければいけないのは「行動」です。脳の部位を特定した、とても小さい神経細胞の反応をとり、これに対応する行動を考えるためには、行動のほうもすごく短い時間で変化するものを対象にする必要があります。そこでたとえば僕らがやってみたのは、ちょっとした変化で見える・見えないが一瞬で変わってしまう「錯視」です。四角形を描かずに4つ角を強調するバーチャルな図形を作り、その内側に四角形を錯視できるかどうか、マウスに反応させます。脳のどの領域で反応が起こるかを確認した後で、その部位をオフしたら、急に四角形が見えなくなれば、行動との関与が示唆されますね。
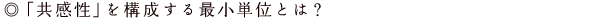
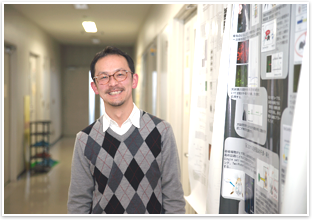 記憶のメカニズムは90年代までにいろんな研究が現れ、神経細胞同士がつながることが記憶を構成する基本的なメカニズムだろうという理解を残して、ある程度落ち着いていきました。では次の大きなテーマは何だろう? というと「情動性」や「社会性」が注目されてきています。ところが「情動性」と言った途端に、なぜか文学的なニュアンスが出てくるんですよね(笑)。「情動性って何ですか?」と。僕も実は情動性というものはないし、あるいはもっと細かく分解し、コード化して説明するべきだと思っています。
記憶のメカニズムは90年代までにいろんな研究が現れ、神経細胞同士がつながることが記憶を構成する基本的なメカニズムだろうという理解を残して、ある程度落ち着いていきました。では次の大きなテーマは何だろう? というと「情動性」や「社会性」が注目されてきています。ところが「情動性」と言った途端に、なぜか文学的なニュアンスが出てくるんですよね(笑)。「情動性って何ですか?」と。僕も実は情動性というものはないし、あるいはもっと細かく分解し、コード化して説明するべきだと思っています。
これに関連して、今、共感性の進化神経基盤の解明といったテーマにも取り組んでいます。この「共感性」も「それ、具体的に何ですか?」を考える必要がありますね(笑)。一般的には「情動伝染」と呼ばれる──たとえば他人が足の小指をガンっと打ったのを見て、自分も痛い気がするといった現象──がコアにあって、これに認知的なプロセスが加わって、シンパシーやエンパシーが出てくるのではないかと言われています。僕らの実験は、マウスに電気をビビッと流して「痛い」と思ったことを、別のマウスがどう共感するかを具体的にとっています。しかし、そもそも僕ら人間がネズミを見て「共感してる」と言っている時には、あからさまに擬人化して見てるだけの話で、共感かどうかも分からない!(笑)そのくらいの懐疑はいつも持って、まず、一見僕らが擬人的に「情動」や「共感」と思ってしまうことを、具体的な行動として取り出す作業を進めています。
つまり「共感」という行動があるわけではなくて、情報を科学的に記述できるような行動の形があると思うんです。外部からの情報があって、記憶との参照や、内部情報との参照を行うことが進行したときに、僕らが「共感っぽい」と思うような現象となって現れる。そういったひとつひとつの情報処理がどういう一連のこととして流れているかを解明しないと、脳の情報処理と関連付けて説明できないと考えています。また生き物によって形態や生態が違うので、どの特徴量に注目するかはさまざまですが、基本的なやり方は──例えば、ディッシュの上の神経細胞の突起の伸ばし方も、人の表情の解析も──同じだと思っています。何をやらなければいけないのかをちゃんと考えて、次につながることをやりたい。今、その基本的なコンセプトをつくり込んでるところです。






