教育学部における、教員養成を目的としない課程。その再編、見直しが迫られている。教員免許取得を目指さない教育学部の存在は、社会の中でどのような役割を担ってきたのだろうか。そして廃止は、社会にどのような影響をもたらすのだろうか。
教育学部の機能を概観し、これまで果たしてきた役割、そしてこれからの社会で果たす役割について勝野正章教授に聞いた。

 教育学部には、旧師範学校の流れをくむ教員養成を目的としたコースのほかに、教員免許の取得を卒業要件としない、いわゆる「ゼロ免課程」と呼ばれる課程があります。ゼロ免課程を卒業した人は、地元の一般の企業などに就職して会社員になるといった進路を選択しています。今年6月、文部科学省は人文社会系学部、教育学部の廃止を盛り込んだ通知を出しました*。この中では、ゼロ免課程を廃止することが一つの柱となっています。この背景にあるのは子どもの数の減少ですが、本音は国の財政的な負担を減らしたいということでしょう。逼迫した予算の中で、教育学部でありながら教員を養成しないコースに対して、厳しい目が向けられているのです。
教育学部には、旧師範学校の流れをくむ教員養成を目的としたコースのほかに、教員免許の取得を卒業要件としない、いわゆる「ゼロ免課程」と呼ばれる課程があります。ゼロ免課程を卒業した人は、地元の一般の企業などに就職して会社員になるといった進路を選択しています。今年6月、文部科学省は人文社会系学部、教育学部の廃止を盛り込んだ通知を出しました*。この中では、ゼロ免課程を廃止することが一つの柱となっています。この背景にあるのは子どもの数の減少ですが、本音は国の財政的な負担を減らしたいということでしょう。逼迫した予算の中で、教育学部でありながら教員を養成しないコースに対して、厳しい目が向けられているのです。
ゼロ免課程が設置されたのは1980年代後半です。このころは、子どもの数の減少が見込まれ、それまで大きな課題となっていた教員数の拡充が一段落した時期です。しかし、簡単に教育学部を廃止することはできなかった。そして、幅広い教養を備えた人に、一般企業でも人事、研修といったところで力量を発揮してもらうという意図で、必ずしも教師になることを目的としない教育学部の役割が設定されたのです。実際、理系、文系を問わず学際性のある幅広い知識や人の発達や成長に関わる知見などの教養を身につけた人材が、企業にも求められてきたという構造があったのです。
ところが、文科省は、教育学部は教員の養成に特化せよという通知を出しました。
教育学は、経済学や行政学、心理学、脳科学など多岐にわたる人文科学系学問や自然科学などを基礎にしている幅広い学問領域です。ですから、教育学そのものが個別具体的な能力を育成したり、特定の社会課題を解決するといったことはあまりないと思います。しかし、そのような広範な学問領域を基礎とした教育学的教養が社会にもたらしてきた影響は決して軽んじられるものではないはずです。
とくに、現在の世界は将来への見通しが不透明で、一つの明確な解が問題のすべてを解決できるという状況ではありません。複雑で難解な課題に直面することが予想される今、自ら課題を見つけ、その解決のために考えたり行動したりする力をもった人材の育成が求められるようになっています。専門性だけを強調し教養をおろそかにしてしまうと、全体を俯瞰せず、結果的に上から言われたことに従うだけのクリエイティビティの低い人材を生み出す可能性もあります。
*「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて(通知)」2015年6月8日
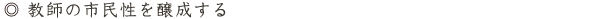
 最近、教育の分野では、アクティブラーニングということがさかんに言われるようになりました。「なにを知っているか」だけではなく、「知っていることを使ってどのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」ということに力点を置いて、知識、技能、思考力、判断力、表現力を身につけさせるという目的で提唱された考え方です。学校の授業においても、社会に目を向け、課題を見つけてその解決のために考えるということが求められます。
最近、教育の分野では、アクティブラーニングということがさかんに言われるようになりました。「なにを知っているか」だけではなく、「知っていることを使ってどのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」ということに力点を置いて、知識、技能、思考力、判断力、表現力を身につけさせるという目的で提唱された考え方です。学校の授業においても、社会に目を向け、課題を見つけてその解決のために考えるということが求められます。
このような授業を実現するためには、教師自らが社会と関わりを持ち、教材を作成するクリエイティビティの高い取り組みが求められるでしょう。しかしながら、現状はそれに向けた環境が整っているわけではありません。その問題の一つとして、日本の教師は、自らの考えや視点を表現することが過度に制限されている、ということがあります。人権を制限されていると言ってもいい。もちろん、教師の立場や授業という場を使って、教師が自分の考えを押しつけることは、あってはならないことです。しかし、過度に中立性を求めることにより、社会や政治に関する考えを述べることもできない、そうしたテーマを授業で扱うこともできないのが現状です。少なくとも、「自分はこう思うけれども、他にもこういう考え方がある、どう考えるか?」といった立ち位置で、社会で起こっている事柄に関して子どもたちが身近な問題として向き合えるような、そして解決のための意欲も同時に育つような授業を作るには、教師自身も、市民でなければなりません。
自分たちが考え行動することによって社会にコミットする人材を育てるには、「機能する民主主義」を定着させなければなりません。子どもたちに、自分たちの力で社会を創っていけるという自己効力感をつけさせたり、権利とは何か、どのように行使するのかといったことをきちんと伝えたりする必要があります。それをしないで、「国民には〇〇権、△△権があります」というだけの、「カタログ」のようなものを見せたところで、権利の本質は伝わらないし、子どもたちの力にはなりません。
OECD(経済協力開発機構)によるTALIS(国際教員指導環境調査)では、日本の教師は、子どもの、勉強への自主性や興味・関心を引き出したり、学校の規律を保持したり、さまざまな指導方法や評価方法を工夫して用いることができる、といった実感が低いという結果が出ています。また、自身の仕事への満足感も国際平均をはるかに下回っています。自分の職業が、子どもたちを成長させていると感じる「自己効力感」が非常に低いということです。教師自身の裁量や視点、創造性の高い授業に対する理解が得られないまま、子どもたちに、思考力・判断力、表現力をつけさせることを求める構造には矛盾があります。
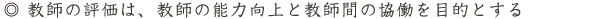
 教師は専門職です。専門職であれば、当然自らの能力を高め、質のよい教育を行うために努力しなければなりません。思考力、判断力、表現力、社会へのコミットといったことを求めながらも、たとえば国際的なテストの点数が教育の質や教師の評価指標として使われるのもおかしなことです。
教師は専門職です。専門職であれば、当然自らの能力を高め、質のよい教育を行うために努力しなければなりません。思考力、判断力、表現力、社会へのコミットといったことを求めながらも、たとえば国際的なテストの点数が教育の質や教師の評価指標として使われるのもおかしなことです。
教師がおかれている環境についてはすでに述べましたが、そうした現状を容認しながら、教師の質を評価するのに、人事考課を用いるということには反対です。それでは、ますます教師の裁量を狭めることになりますし、創造的な授業を行うための弊害になってしまうでしょう。何らかの評価は必要ですが、教師が専門性を発揮できるように支えるしくみがなければなりませんし、それには教師同士が学び合い、能力を高めていくための場や方法論、そして余裕が必要なのです。そういう状況を改善せずに、免許更新制などを導入して人事考課や雇用といったことに言及されるような評価方法を続けていては、教師が専門職としての能力を発揮することはできません。
能力の低い教師に対しては、教師同士が信頼感に基づいて学び合い、質を上げていく。個人の能力だけを測るのではなく、集団として力を発揮できるようにするなど、課題は数多くあります。
教師が身につけるべき素養は、教科に対する知識や教える技術はもちろんのこと、子どもたちの理解、そして幅広い教養など多岐にわたります。今後さらに複雑になっていく社会。そこで生きていく子どもたちが身につけるべき力はますます増えていきます。教師はこれまで以上に高度な内容を理解して伝えることが求められます。そうした、すぐに数値化したり結果を見ることができない要素に価値を見いだすには、教育に対する社会の理解や、社会における教育学の有用性が共有されるべきで、その意味からもさまざまな学問の成果を統合させるという観点から教育学部を見ていく必要があると思います。
自分自身が学ぶ技術の獲得と、知識や技術を高め幅広い教養を身につけさせることが、教育学部の重要な役割といえます。この場合の「教養」は、エリートだけが持っていればよかった古いタイプの教養主義とは一線を画すものであり、誰もが直面する社会的課題に対応できる、皆が持っていなければならない市民的教養を意味します。このような背景からも、教育学部の役割は時代に応えるものになり得るでしょう。






