高校の時にカンボジアやベトナム難民のニュースに関心を持ったことがきっかけで、大学では旧宗主国の言語であるフランス語を専攻。大学3年から2年間チュニジアの日本大使館で派遣員として生活し、アフリカはおもしろいところだと芯から思ったという、日本貿易振興機構(JETRO)アジア経済研究所 地域研究センターの武内進一アフリカ研究グループ長。だが「自分は何をおもしろいと思ったんだろう?」そんな問いから人々の暮らしへの興味を軸に、2つのコンゴ、ルワンダ、ガボン、ブルンジといった国々のある中部アフリカを対象とした地域研究が始まった。研究所のある幕張でお話を伺った。

 アフリカの地図を見ると、最初は特に何とも思わないけれども、徐々に不思議な国境線だということに気づいていきます。アフリカで、国の形は重い意味を持っています。もちろん植民地分割の結果によって国のかたちが決まってきたわけですね。そんな国の一つであるコンゴ民主共和国(旧ザイール)が自分のフィールドだと考えて、ではこの辺りの人たちはいったい何を食べているんだろう? というのが最初の研究課題でした。主食はキャッサバというイモで、実はタイなど東南アジアでとれるタピオカのことなんです。原産地は中南米で、14〜15世紀頃、奴隷貿易を期に入ってきて、それ以前の主食であった雑穀に取って代わってしまう。
アフリカの地図を見ると、最初は特に何とも思わないけれども、徐々に不思議な国境線だということに気づいていきます。アフリカで、国の形は重い意味を持っています。もちろん植民地分割の結果によって国のかたちが決まってきたわけですね。そんな国の一つであるコンゴ民主共和国(旧ザイール)が自分のフィールドだと考えて、ではこの辺りの人たちはいったい何を食べているんだろう? というのが最初の研究課題でした。主食はキャッサバというイモで、実はタイなど東南アジアでとれるタピオカのことなんです。原産地は中南米で、14〜15世紀頃、奴隷貿易を期に入ってきて、それ以前の主食であった雑穀に取って代わってしまう。
首都キンシャサ(Kinshasa)は大陸の西側、コンゴ川の河口寄りにあるんですけれども、キャッサバが農村でどう作られて、どう首都にやってくるか、食料の生産・流通・消費の流れを調べようと思った。ところが私が研究を始めた1980年代半ばから、ザイールの政治経済情勢はどんどん悪くなっていきました。結局、1991年に大暴動が起こり、首都のキンシャサにあった商社も大使館の人たちもみんな逃げてしまう。これではキンシャサに住んで調査するどころの話ではない。キンシャサはコンゴ川という大河のほとりにある都市で、その川向こうには、ブラザヴィル(Brazzaville)という、隣国(コンゴ共和国)の首都がある。町の規模としてはずっと小さいのですが。私はそちらに赴任して、食糧に関する調査を続けることにしました。1992年の秋のことです。ところがブラザヴィルに赴任してしばらくしたら、まただんだん雲行きがあやしくなってきました。
1990年代初頭のアフリカはどの国も政治が不安定で、ブラザヴィル・コンゴも内戦になってしまいます。内戦といってもいきなりドンパチ始まるのではなくて、デモをしているところに発砲があって何人かが死に、するとデモの規模が拡大して衝突が激しくなり、遂には武力衝突に至るというパターンです。ちょうど私が住んでいた辺りで2つの勢力がせめぎ合い、装甲車や戦車が通ったり、機関銃の掃射などもしばしばでした。逃げたりもしなくてはなりません。つまり自分は市場を調査しながら、一方では紛争状況の中に生きている。助手として一緒に働いているコンゴ人たちも、やはりその中で暮らしている。そのようなさまざまなつながりの中で、紛争の中でどういう連中がどういうことをやっているのかということを、否応なく見聞きしました。
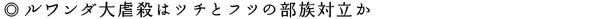
 結局1年半ぐらいでブラザヴィル・コンゴでの調査はあきらめざるを得なくなって、1994年の4月に、その西にあるガボン共和国へ移りました。ちょうどその時期にルワンダで大虐殺があり、ガボンにいる時は、ずっとルワンダのニュースが流れていたんです。そして半年後に日本に帰ってみると、ルワンダ難民支援のために自衛隊をザイール東部に派遣することが決まっていて、自衛隊派遣を巡ってさかんに議論が行われていた。その一方で、ルワンダ内戦はその背景説明として扱われ、ツチ族とフツ族の部族対立の結果だという言い方でもっぱら済まされてきたわけですね。私は、ブラザヴィルで、やはり部族が重要な位置づけを持つような武力紛争を体験してきたわけですが、エスニシティそのものよりも、それを動員する政治の力が重要だということを強く感じていたので、ルワンダ内戦の説明にはすごく違和感を持った。そうじゃないだろうという感じがしたわけです。
結局1年半ぐらいでブラザヴィル・コンゴでの調査はあきらめざるを得なくなって、1994年の4月に、その西にあるガボン共和国へ移りました。ちょうどその時期にルワンダで大虐殺があり、ガボンにいる時は、ずっとルワンダのニュースが流れていたんです。そして半年後に日本に帰ってみると、ルワンダ難民支援のために自衛隊をザイール東部に派遣することが決まっていて、自衛隊派遣を巡ってさかんに議論が行われていた。その一方で、ルワンダ内戦はその背景説明として扱われ、ツチ族とフツ族の部族対立の結果だという言い方でもっぱら済まされてきたわけですね。私は、ブラザヴィルで、やはり部族が重要な位置づけを持つような武力紛争を体験してきたわけですが、エスニシティそのものよりも、それを動員する政治の力が重要だということを強く感じていたので、ルワンダ内戦の説明にはすごく違和感を持った。そうじゃないだろうという感じがしたわけです。
それで1990年代の後半から、研究のテーマをアフリカの紛争問題へと徐々にシフトさせていきました。そして人類学の方など何人かとの共同研究を組織して、成果をまとめました。その一方で、紛争や戦争に直接関わる学問をもっときちんと勉強しなくてはという気持ちも強く、30歳代の終わりから大学院に入り直して国際関係論を勉強したんです。大学院では、研究業務と並行して、紛争に関わる学問体系を理解したいと思って勉強しました。長期滞在はできなかったのですが、1998年から毎年1ヶ月ぐらいはルワンダに入って調査を続けました。その中で、ルワンダで調査しようとすると、政治的な制約がきわめて強いこともわかってきました。
そこで、政治や紛争を正面には掲げず、しかしそれらに深く関わる研究テーマということで、土地の問題をやり始めたんです。ルワンダでは人口が多く土地が稀少で、虐殺の際にはツチの人たちを殺せば土地が手に入るといった煽動が結構あったんですね。加えて、紛争後の政権は土地の大規模な再配分をするなど、ラジカルな土地政策を実行してきました。ルワンダのジェノサイドについて、土地をめぐる国家・社会関係にも力点を置きつつ博士論文をまとめましたが、その後も、土地問題を通じて紛争後の平和構築を見る仕事を続けています。ここでは、なぜ紛争が起こったのかという論点を踏まえて、紛争を繰り返さないためにはどうすればいいのかということを考えようとしているんだと思います。

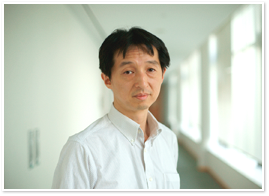 研究を通じて、われわれは大変な時代に生きているということを強く感じています。アフリカの人もそうだし、われわれ自身もそうです。今日の時代性は恐ろしく底が深くて、戦争も平和もその中にある。二十世紀初めから戦争の違法化に向けた国際社会の努力が続けられてきましたが、その結果、国家間紛争は大幅に減ったものの、アフリカなどでは、昔であれば滅亡したような脆弱な国家が存続し、統治能力の弱さから国内紛争が繰り返されています。人間がよかれと思ってトライしたことの帰結が何だったのか?──いい悪いを問うこと自体が難しいものにいっぱい囲まれて、われわれは生きている。そのことに自覚的であろうとする時、アフリカは、ひとつの重要な入口だと思います。自分たちがどういう時代に生きていて、そこにはどんな難しさがあるのか。それを知ることは、まずは自分のために、とても必要なことだと思うんです。
研究を通じて、われわれは大変な時代に生きているということを強く感じています。アフリカの人もそうだし、われわれ自身もそうです。今日の時代性は恐ろしく底が深くて、戦争も平和もその中にある。二十世紀初めから戦争の違法化に向けた国際社会の努力が続けられてきましたが、その結果、国家間紛争は大幅に減ったものの、アフリカなどでは、昔であれば滅亡したような脆弱な国家が存続し、統治能力の弱さから国内紛争が繰り返されています。人間がよかれと思ってトライしたことの帰結が何だったのか?──いい悪いを問うこと自体が難しいものにいっぱい囲まれて、われわれは生きている。そのことに自覚的であろうとする時、アフリカは、ひとつの重要な入口だと思います。自分たちがどういう時代に生きていて、そこにはどんな難しさがあるのか。それを知ることは、まずは自分のために、とても必要なことだと思うんです。
2009年から3年間は国際協力機構(JICA)の研究所にいて、「平和と開発」という大きなテーマの下で研究をしました。そのなかで、平和構築の研究や実践が、治安部門改革(Security Sector Reform: SSR)、武装解除・動員解除・再統合(Disarmament, Demobilization, Reintegration: DDR)、民主化といった国家レベルの大きな問題に集中していることに気がつきました。こうしたテーマはもちろん重要なのですが、その一方、平和構築を考える上で、ふつうの人々が日常的に直面している安全保障に関わる問題にもっと目を向けるべきだ、と強く思うようにもなりました。この関心は、直接的には、武力紛争経験国の平和構築に向けられたものですが、われわれが暮らす世界までつながっていると思っています。武力紛争という極端な状況がなくても、人々が日常的に直面する安全保障という面では、治安をはじめいろいろな問題があるし、日本ならたとえば民主主義の質とか防災、さらには医療におけるクオリティ・オブ・ライフといった問題にもつながってきます。
アフリカの紛争や部族をめぐる問題は、自分としては、日本の問題としても考えているつもりなんです。もう10年以上前になりますが、九州の離島で選挙を巡って乱闘が起こったことがあります。選挙が住民を二分する土地柄で、勝った陣営が町役場の主要ポストを独占して公共事業を発注する。選挙の結果が生活に直結するから、選挙がヒートアップし、僅差の結果をめぐって暴力沙汰になる。この事件は、私がアフリカのブラザヴィルでみたのと同じ構図です。部族が対立しているように見えても、政治家に連なる利権配分のネットワーク同士の衝突になっている。外国人としてある地域をみることは、意識するしないに拘わらず自分の生まれ育った環境と比較していて、視線が相対化されているんですね。アフリカの事例を参照することによって、日本で起きていることがよりクリアに理解できる──そんなことも、人に伝える意義があるのではないかと考えています。






